企業法務のご相談も受付中。お気軽にお問合わせください。
非上場企業でも粉飾決算は起こり得る|粉飾決算の背景と法的責任

1.非上場企業でも粉飾決算は起こり得る
粉飾決算と聞くとどのような事件を想像されるでしょうか。
テレビや新聞などでの報道で取り上げられるような粉飾決算は、多くの場合上場企業において起きたものです。
しかし、粉飾決算は上場企業だけで起きるものではありません。
東京商工リサーチが2019年11月11日に発表した調査によると、2019年1月から10月までの間に、粉飾決算を一因として倒産した事例は、前年の2倍にのぼったといいます。
このように非上場企業においても実際に粉飾決算が起きていることがわかります[i]。
この記事では、非上場企業(株式会社)について、粉飾決算が起きる背景とともに、粉飾決算に伴う法的責任について取り上げます。
2.非上場企業が粉飾決算をする動機と正当化
一般論としてですが、非上場企業が粉飾決算をして利益を多く見せかける動機はあまりないとも考えられます。
非上場企業の場合、利益を多く見せかける粉飾決算とは逆に、むしろ税引前利益ひいては課税所得を少なくして、税金の負担を少なくしたいと考えることの方が多いといえるでしょう。
しかしながら、非上場の企業が粉飾決算を行うこともしばしば見られます。
その動機として多いのは、銀行などの金融機関から融資を受けるうえで、会社の業績を良く見せかけることで、融資を受けやすくすることでしょう。
事業を継続していくうえで、会社の運転資金は不可欠であり、資金が不足して支払不能になれば倒産してしまいます。
そこで、粉飾決算の実行者は、倒産するくらいならばと粉飾決算を正当化し、金融機関を欺いて融資を受けようとするのです。
このように、粉飾決算をはじめ不正が起きる背景には通常、動機・正当化といった要素があります。
動機・正当化に、機会を合わせて不正のトライアングルと呼ぶこともあります。また粉飾決算においては他にも正当化が伴うことがあります。
例えば、粉飾決算の手法として、本来は次年度に計上するべき売上を、当年度の売上として不正に前倒しして計上するような手法がとられることがあります。
この場合、実行者の心の中では、次のような正当化が行われていると考えられます。
一つには、前倒し計上した売上はいずれ計上されるべきもので架空のものというわけではないというもの。
また、前倒し計上しても次年度の売上を頑張って伸ばし埋め合わせればよいというような正当化もあり得ます。
3.非上場企業の粉飾決算と法的責任

(1)刑事責任
しかし、粉飾決算の実行者がいくら自らを正当化したところで、粉飾決算によって金融機関を欺いて融資を受けたのならば、詐欺罪(刑法第246条第1項(10年以下の懲役))に問われる可能性があります。
粉飾決算に伴う刑事責任としては、他に会社財産を危うくする罪(会社法第963条(5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はその両方))や特別背任罪(会社法第960条(10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はその両方))の成立も考えられます。
(2)過料
なお、会社法976条には、貸借対照表、損益計算書等に虚偽の記載をした者を100万円以下の過料に処するとの規定があります。
過料は刑事罰ではありませんので、その意味で刑事責任ではありませんし、前科になることもありません。
(3)民事責任
粉飾決算によって損害を受けた人や会社がある場合、民事上の責任も追及される可能性があります。
非上場の会社の場合、民事上の責任として代表的なものは、会社法429条に基づく責任です。
会社法429条は、取締役をはじめとする役員等の第三者に対する責任を定めていますので、これに基づいて損害賠償請求をされる可能性があるのです。
なお、粉飾決算を実行した経営者がこのような民事上の責任を追及されるのは当然ですが、粉飾決算を発見すべきであったのにできなかった他の役員が責任を追及される場合もあります。
粉飾決算の場合には、通常は会社法429条2項の規定により、役員等の側が注意を怠らなかったことを自ら証明しなくてはなりませんので、この点にも注意が必要です。
また、非上場企業の場合でも会計監査を受けていれば、会計監査人の責任が追及される場合[ii]もありますし、決算業務に関わっていた税理士の責任が追及された事例[iii]もあります。
4.従業員が粉飾決算を主導する場合も
また、ここまでは経営者が粉飾決算を主導する場合を想定していましたが、実際には従業員が粉飾決算を主導して実行する場合もあります。
これは例えば、従業員自身の成績評価が業績に連動している場合に、業績を良く見せかけることで、自分の成績評価を引き上げようとする動機などによるものです。
従業員が主導してやったからといって、経営者が責任を負わないわけではありません。
経営者には会社の内部統制を整備し、社内で不正が起きないようにする義務がありますから、従業員が不正を行った場合には、経営者はこのような義務を怠った責任を負うことがあるのです。
このように、粉飾決算が起きた場合、上場企業はもとより、非上場企業であっても、多くの関係者に責任が及ぶことになります。
5.粉飾決算は隠し通せるものではない
粉飾決算が多くの法的責任を伴うと聞くと、景気が良くなるまで隠し通そうだとか、自分の役職在任中は隠し通そうだとか、中にはそのようなことを考える方もいるかもしれません。
しかし、粉飾決算をしていれば、決算の中に歪んだ部分が生じます。1年分の決算書だけを見てわからないようなことであっても、数年分の決算書を並べて見たりすれば、売上高に比べて売掛金が異常に多くなっているだとか、在庫が異常に多くなっているということはわかりやすくなります。
金融機関は融資先企業から提出された決算書などを分析していますから、異常な点に気付いたならば、金融機関としても当然その原因を調査しようとするでしょう。
経営者が、従業員主導による粉飾決算を発見しようとする場合であっても、上記のような視点は大切です。
自社の業績について報告を受けるうえで、売上が増えているとか、利益が増えていることも大切ですが、売掛金や在庫などの関連数値が異常な動きをしているようであれば、担当者にその原因を問い質すのがよいでしょう。
このように粉飾決算による歪みは、決算の中に数値の動きとしてあらわれますから、隠し通せるものだとは思わない方がよいでしょう。
決算全体の中で粉飾決算の金額が少なければ、そのような歪みは目立たないかもしれませんが、粉飾決算の金額が多くなるほど、歪みは目立ったものとなりますから、数値の異常な動きもわかりやすくなっていきます。
6.粉飾決算から抜け出すことは難しい
粉飾決算を始めた当初は、粉飾決算はあくまで一時的なもので、今後順調に業績を伸ばしていけば解消できるかのように実行者は考えがちなものです。
しかし、実際には順調にはいかずに、さらに粉飾決算の金額が膨らんでいくことも多いのです。
このように粉飾決算は一度始めると抜け出せない恐ろしさがありますから、もし既に粉飾決算を行っているのであれば、経営者が粉飾決算から抜け出す決断をして、膿を出し切る作業をしなくてはなりません。
これは自身が粉飾決算を始めてしまった場合でも、先代経営者や幹部従業員が始めてしまった場合でも基本的に同じです。
もちろん長年に渡る粉飾決算の全体像を調査して、正しい決算を作成する作業や、過大に申告納税していた税金の還付、金融機関など利害関係者への説明・対応、再発防止のための体制作りなど、やらなければならないことは多岐にわたります。
このような危機対応には、弁護士・公認会計士・税理士など外部の専門家の助力を得ることを考えるとよいでしょう。
しかし、粉飾決算のような企業不祥事は、外部の専門家だけで解決できるものでは決してありません。経営者の決断力こそが解決のための必要不可欠な要素なのです。
[i] 日経電子版の記事(https://www.nikkei.com/article/DGXMZO53447250X11C19A2000000/)参照。
[ii] 粉飾決算をした会社に融資をしていた銀行が、当該会社の会計監査人に対して、粉飾決算を発見すべきであったのにできなかったとして、商法特例法10条に基づく責任(現在の会社法423条1項に定める会計監査人の責任に相当します。)を追及した裁判例として、東京地裁平成19年11月28日判決があります。もっとも、この裁判例では、結論として会計監査人の責任は否定されました。
[iii] 仙台高裁昭和63年2月26日判決。この事例では、会社の顧問税理士が、税務署に提出する赤字の確定申告書とは別に、債権者に提出するための黒字の虚偽の確定申告書も作っていたという事情が認められ、当該税理士の責任が認められました。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
関連記事

カスタマーハラスメントとは?クレームとの違いや企業の対応策を解説

カスタマーハラスメントの主な事例とは?企業がとるべき対応策も解説
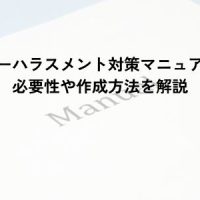
カスタマーハラスメント対策マニュアルとは?必要性や作成方法を解説






