企業法務のご相談も受付中。お気軽にお問合わせください。
企業法務で知っておきたい合弁契約のポイントと実際の体験談について
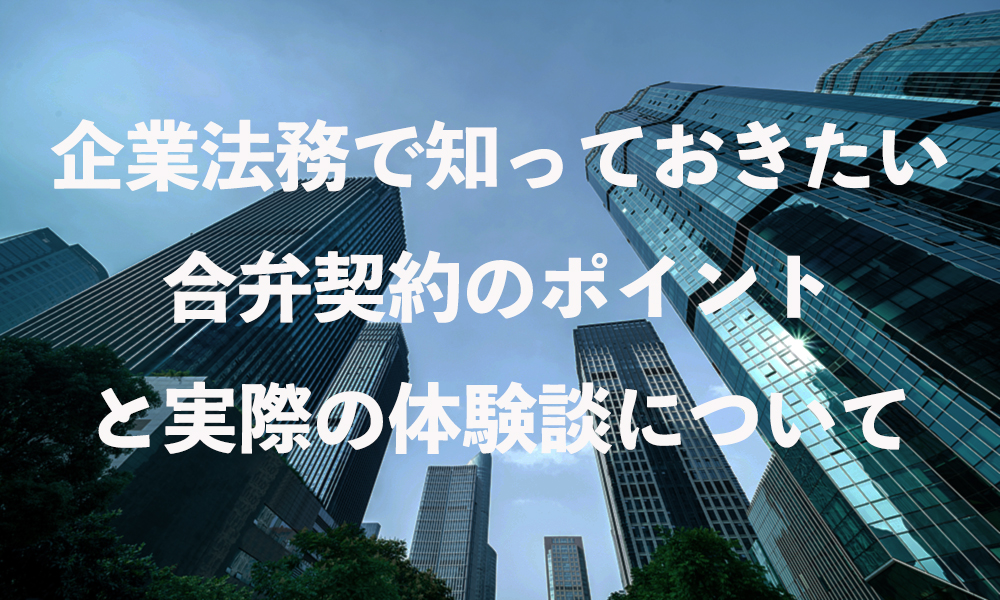
1.はじめに
合弁契約について、ちょっとした軽い感じの散文を綴ってみました。企業法務に興味をお持ちの方には、参考になることも書いていると思いますので、気楽にお読みください。
2.「合併」と「合弁」

(1)紛らわしい言葉
ビジネスマンとして、時として、紛らわしい言葉に出会うことがあります。この「合併」と「合弁」もその一例です。
・「合併」
「合併」とは、法人そのもの(法人格といいます。)が複数いわば融合することを言います。
皆様が経営企画室、営業本部や技術開発部等々の会社組織の一部に属しておられる場合、その法人そのもの全てが他の法人と一緒になってしまうというイメージです。法人格が一つになってしまいます。
・「合弁」
一方、「合弁」とは、皆様が属している会社組織自体はそのままで、特定の会社事業部門が、ある事業や商品の開発や販売市場を睨んで、戦略的に、他の法人の同様又は関連部門(こちらの会社も会社組織自身(法人格)は変わりません)と、別個の会社(第3の法人格とでもいいましょうか、これが合弁会社です。)を作って共同事業を行うというイメージです。
このような場合、通常、各法人は、合弁会社に対して、各出資持株を保有して、今後、両出資法人の長所を補強し短所を補い合いながら戦略的に市場に打って出て、合弁会社の企業価値を高めることになります[1]。
(2)「合弁」契約を押さえよう!
振り返ると、ビジネスマンの皆様が関わる法的問題は、圧倒的に、「合弁」会社の問題になるでしょう。
理由は、「合併」は法人格そのものの変動で、一大事で、そう多くは発生しないですし、多くは経営企画、秘書部門や特命担当部所で秘密裡に進めるからです。一方で、「合弁」ももちろん重要で秘密裡に進めるものではありますが、たとえ、ビジネスマンの皆様が、営業部門にいても、製造部門にいても、開発部門にいても、広報部門にいても、会社の各個別事業の推進を戦略的に考える場合、他法人との共同関係はつねに想定できるからです。
実際、合弁に関与したビジネスマンの皆様は多くおられるでしょう。
3. 企業法務マンだった弁護士がみる合弁契約の注意ポイント

(1)注意ポイント
では、今後(いま、まさに課題であるかもしれませんね!)、ビジネスマンの皆様が「合弁」契約を検討するについて、注意すべきポイント何か。
本論考では2点に絞って、お話したいと思います。それは、以下の2点です。
・事業範囲
・先買権規定
(2)検討する2点について
①事業範囲
1)言い忘れましたが、合弁事業を始めるには、両者事業部門のトップの意向を受けたプロジェクトメンバーどうしが協議の上合意した「合弁事業契約」の締結が不可欠です。この合弁契約の中で最大に注意すべきは、合弁会社の「事業範囲[2]」の部分であると思います。
合弁会社の設立交渉は、2つ以上の会社の関係部門の戦略や利害が錯綜する現場です。その戦略や利害が一番先鋭に現れるのが、合弁契約の「事業範囲」です。
2)製品全般に広く技術的に優位な特許やノウハウを保有する会社(A社とします。)は、市場で技術的に優位にある会社で、今後、合弁を戦略的に進めて利益の極大化を図りたいとすれば、合弁契約の事業範囲は「必要不可欠な」事業内容以外は書き込むべきではないでしょう。
3) たとえば、A社は、合弁会社設立時に、A社財産をいかに活かし、自社の利益を極大化するかを睨んでいると思います。つまり、A社は、合弁会社設立では、相手会社(B社とします。)の市場での優位ある地位や製品アプリケーションに魅力を覚え、B社との合弁関係を想定しています。
しかし、A社は、別個のアプリケーションや技術分野では、むしろ、別のC社が適切なパートナーであると考えていたりします。
そのようなこともあって、法的リスクの観点からは、合弁契約では、合弁事業契約の事業範囲は、できる限り、特定しておいた方が、より自由度が大きくなります。
もちろん法的に突き詰めれば、事業独占(又は競業避止)的な契約でない限りは、複数の会社相手に合弁事業を行うことは可能です。法的に拘束がないのであれば、上記のような事業範囲については、そんなに神経質にならないでもいいとの意見もあるかもしれません。しかし、ビジネスの現実を睨んだ場合、特に長い友好関係がある日本企業同士の新規合弁事業の場合は、広く書き込むことでの現実のリスクが生じることもあるので、検討される方は十分な注意が必要です。
とは言っても、会社間のビジネス関係では、広範な協力関係の提案に対して、経営判断で、合意することはありうると思います。経営層が検討するときに、ビジネス判断として、相手会社との信頼関係を高める面からも、特定会社(上記例では相手会社B)との関係を特段に重視して法的なリスクやその他リスクにもかかわらず、経営上の意思決定をすることはあり得ると思います(その時は、競業避止条項の内容に注意してください。)。
4)(具体例)
一例を考えます。A社には電池総合メーカーとして、一次電池及び二次電池(繰り返し使える電池を「二次電池」といいます。)に優位性のある先端技術と特許があります。B社は市場で強大なアプリケーションをもつ電気掃除機メーカーや自転車メーカーです。モーターの駆動源として二次電池の必要に迫られています。二次電池では、鉛電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池という電池系が存在します。
このような例では、合弁契約の事業範囲検討時に、たとえば、「電池全般」とするのと「ニッケル水素電池」のみとするのとでは、大きな違いがあります。つまり、もし、相手会社B社との合弁ではニッケル水素電池を目的にしていてそれで必要十分であれば、事業範囲は、「電気掃除機用(又は自転車用)のニッケル水素電池の開発、製造及び販売」とする選択がとれます。逆に、事業範囲を「電池の開発、製造および販売」と書き込むと、A社の事業戦略に将来足かせになる恐れがあります[3]。
もちろん、背後にはビジネス環境や相手会社との関係性といった経営上最も重要視すべきファクターがあるのは、理解します。ただ、合弁契約検討を任されたビジネスマンの皆様として、ここに提示した上記の視点は、心得ていただきたいところです。
②先買権規定(The First Refusal Right)
1)合弁契約でもう一つ重要な規定は、合弁会社株式の処分の在り方についての規定です。
合弁会社を設立することで、各会社はその会社資産(主なところでは、資金、技術及び人材です。)を投入しているはずです。ということは、この合弁会社を簡単に手放したりまた逆に手放されたりすれば大変なことになります(つまり、会社に多大な損害が発生します。)。特に、機密情報等を開示利用して合弁会社経営を行うのが通例ですので、いくら機密保持義務を課したとしても、簡単に合弁解消に至ると問題を引きずりかねません。
その対応として、多くの合弁契約では、次の2点をあらかじめ合意しておくことになります。
2)株式処分の制限
まずは、合弁当事者による合弁会社の持ち株の処分制限[4]です。
合弁契約の中で、たとえば、「いずれの当事者も、合弁期間中(又は合弁契約締結日から5年間)は、他方当事者の合意がない限り、合弁会社の株式持分を売却、譲渡又はいずれの形態かは問わず処分行為をせず、または、抵当権などの担保権の設定をしないことを合意する。」との条項に合意しておきます。
もし仮に、株式が自由譲渡できるのであれば、もともと想定していた出資目的がそもそも達成できずに、自社資産が無駄になる、自社機密情報が拡散する等の害悪が想定できるからです。
3)先買権規定
先買権とは、聞きなれない方が大半であると思います。
先買権の規定も、合弁契約を検討する場合には、覚えておくべき重要な条項です。
先買権とは、欧米の契約では、ファースト・リフューザル・ライトと言われるものです。合弁契約当事者は、上記のとおり、合弁契約期間中(又は一定期間)は譲渡制限規定を設けます。しかし、時の経過で各社の戦略や目標も変わり、所有している合弁会社株式を売却したいということがありえます。その場合の持株処分の方法を規定したものが先買権です。
大抵の場合、一方の設立当事者としては、合弁契約締結時点、各合弁当事者の構想を踏まえ、相手方がこの会社であるからこそ、この合弁会社を設立したのだということでしょう。そうであれば、合弁契約中に、相手方当事者が合弁会社株式を第三者に売却したい場合は、契約上の義務として、先に、自社に対し、合弁会社株式を譲渡する旨の通知(申込み)をさせることにします。そして、申し込みを受けた自社で購入する意思があれば、他社(第三者)に先行して、その持株を優先的に譲り受けができるとの規定[5]です(ファースト・リフューザル・ライトというのは、最初に株式購入可否について拒否権が与えられているということですね。)。
この申込に際し、譲渡希望者が第三者と合意した売却予定価格又はその他の価格で購入するという条件が付きます。
このことをまとめますと、具体的な順序として、①第三者へ譲渡可能となる事態の発生、②譲渡希望者が相手方へ第三者名称及び譲渡価格等を文書通知、③相手方が先買権を行使する文書での購入意思表示、④先買権での購入意思表示がない場合は、譲渡希望者から第三者への合弁会社株式の譲渡が可能となります。
先買権は欧米の契約を検討していると、この規定だけで3ページ程度の条項を準備していることがあります。先買権を行使しないが購入する第三者を指定する権利があるとか、その時に相手方も同じく自己持株譲渡の申し込みをする権利を持つとかに加え、先買権で株式譲渡が解決できない場合、①純資産価値、②類似会社の比較による想定市場価格、③将来想定される稼得利益を利子率で現在価値に引き直した方法による価格など株式評価の方法の詳細な規定などです。
欧米系の契約は、あらゆる法的リスクへの対応を睨んでドラフトしているようで、正直なところ、複雑で大変です(日本の法人に適した規定であるのかも吟味が必要なのでしょう。弁護士などの専門家にご相談ください。)。
4.企業法務現場のちょっとした話

(1)合弁契約交渉の話について
企業の法務部門、法務マンとしては、株式譲渡についても、法的リスクを少なくするように、できるだけ完璧な契約構成を考えて、相手会社との合弁契約交渉に臨むものです。
しかしながら、ビジネスは常に動いていて、たとえ「合弁」という一事業分野の合従連衡であっても、会社全体への有形無形の影響はあるものです。
これは私の経験ですけれども、ある会社との合弁交渉では、欧米の先買権規定(ものすごく複雑な条文のモノです。)を準備して臨んでいたのですが、結果として、最終合意された合弁契約に規定された条文は、「各合弁当事者がその持株を譲渡しようとする場合は、両当事者が誠実に協議して、その条件を決定する。」という簡単なものでした。
(2)ビジネスとの関係について
常にビジネスは生きています。したがって、経営判断として、会社全体での最適を決意して交渉されるものだろうと思います。私は、企業法務マンとして、当時を振り返るとき、多くの経営者は、法務部門からのブリーフィングを受け、契約上のリスクへの認識も踏まえながらも、相手会社と多くの分野で協業関係にあったという背景もあり、相手会社との総合的な協力関係の大切さを重視して、契約交渉でも、様々な踏み込んだ決断をされたのであろうと思います。
そう考えれば、企業法務マンとしても、随分、納得感もありました。もちろん、その前提として、交渉前の事前打ち合わせで、企業法務マンとしては、契約上のリスク、合弁契約で記載すべき条項の内容と趣旨は、理由付きで経営者に説明しておくことは不可欠であると思います。当時、最終合意条文を見たとき、驚きましたが、ビジネス関係構築の大切さと企業間交渉の奥深さを痛感した瞬間でした。
5.最後に
皆さまの会社で、合弁事業契約に限らず、契約及び法務面で、法的なリスク評価や専門家の見解・判断を聞いてみたいと思われる場合は、お気軽に、弊所の弁護士まで、ご相談を頂ければと思います。具体的に、お役に立てるアドバイスができるものと考えております。
皆様には、この記事をご一読いただき、ありがとうございました。
[1] ちなみに、法律用語辞典等での定義は、「合併」は、「複数の会社が契約により合体して一つの会社となること」です。「合弁」は、「合弁事業各参加者の役割を決め、各当事者が負う責任や得られる利益の範囲を明確にし、事業を円滑に運営するための合意のこと」です。
[2] 会社定款の「目的」規定に相当します。合弁会社設立に、合弁契約と会社定款が関係しています。通常、定款の「目的」と合弁契約の事業範囲の規定は同じになります。しかし、定款の「目的」の登記の関係で厳密には同じでない場合もあります。
[3] 合弁会社事業範囲内の事業を出資当事法人が合弁会社と別に行うことは本来自由です。しかし、ビジネスの実態によれば両社に友好的な関係が維持され、複数商品で協力結合関係があり、他のビジネスで広い協力関係がある場合は注意が必要でしょう。実態として、設立した合弁会社の事業範囲と同じ事業を、自社で行う又は他社と始めることが困難なことが往々にしてあります。一方で、合弁契約の中で競業避止義務条項に合意した場合は、法的責任を問われる場合がでてきます。また、合弁契約での競業避止義務の合意にあたっては、市場に競争制限的な状況がある場合は、製品販売市場である関係国の競争法規制に服する場合があります。
[4] 株式は自由譲渡が原則(会社法127条)です。定款で譲渡制限は可能(非公開会社)です。
[5] 合弁契約に先買権規定が必要な理由は2点あります。第1に、株式譲渡が可能となった段階で、リスクが生じるかもしれない、未知の第三者に合弁会社株式が譲渡されることを、先買権規定でストップできることです。第2は、会社法規定に基づく譲渡実現を阻止できることです。合弁契約で、持株譲渡希望当事者に対する譲渡制限は可能です。しかし、会社法では、定款による譲渡制限がある株式(会社法107条1項1号、108条1項4号)に対し、譲渡承認請求の方法が規定されています。譲渡希望当事者からの承認請求があり、合弁会社が買い取らない場合で合弁会社が買取人を指定する場合(140条1項4項)、取締役会設置会社では取締役会決議で可能になります(140条5項本文)。相手方譲渡希望当事者が取締役会の構成員の関係で承認決議の取得ができるならば、いずれにしても、株式譲渡は実現します。先買権があれば、先行して、これを封じることができます。以上から、先買権規定により、合弁会社での将来の不安定要素を除去できることとなります。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
関連記事






