企業法務のご相談も受付中。お気軽にお問合わせください。
解雇理由及びその提示について|企業側が解雇する際に注意すべきこと
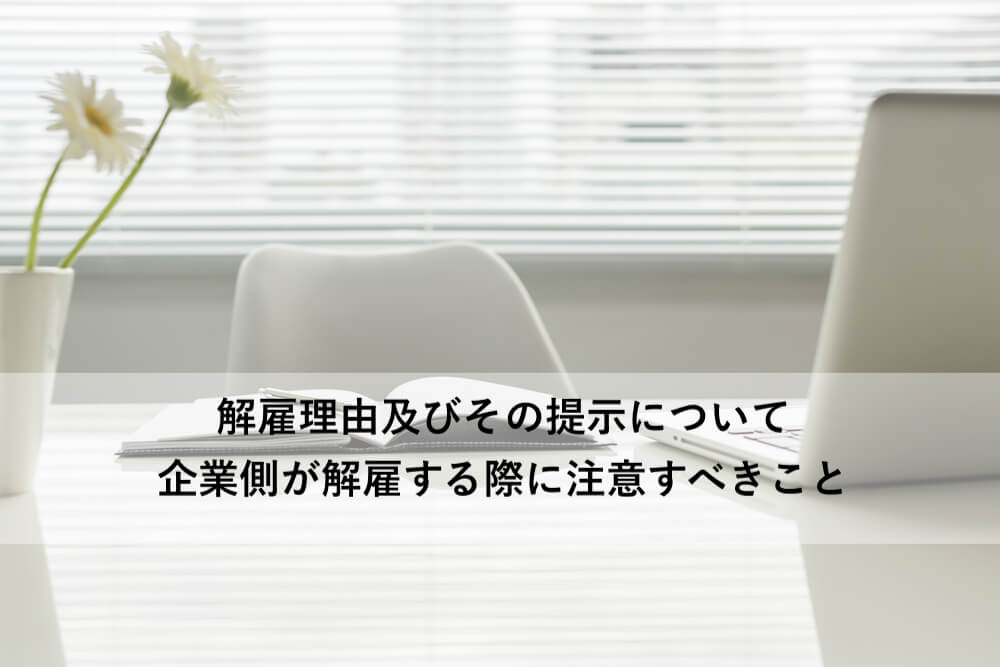
経営者としては、時として労働者を解雇したくなるということもあるでしょう。
しかし、労働者の側からすると、解雇されれば、職を失うという深刻な打撃を受けることとなってしまいます。
そのため、解雇された労働者は、会社側に対し、復職や金銭補償を求めて交渉を求めてきたり、場合によっては、労働審判や訴訟を提起してくることもあります。
そのようなことになれば、会社側は交渉、労働審判、訴訟に応ずるために、多くの時間を取られる等の思わぬ負担を被ることとなってしまいます。
そして、そのような解雇をめぐる争いの中で、主に争点となってくるのが、解雇の理由です。
法律上も、解雇の要件として、「客観的に合理的な理由」を要求しています(労働契約法16条)。
また、一種の制裁罰としての解雇である懲戒解雇の場合においても、同様に「客観的に合理的な理由」が必要です(労働契約法15条)。
労働者側から解雇理由の開示を求められたり、労働審判や訴訟が提起されたりすれば、会社側が労働者の解雇に理由があることを示さなければなりません。
そこで、本稿では、解雇をめぐる争いの中で、主に争点となる解雇の理由、及び会社からの理由の提示の時期、方法にスポットを当てて解説していきます。
1.解雇の要件について
解雇の要件については、労働契約法16条に定めがあり、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定められています。
すなわち、解雇が有効となるためには、①客観的に合理的な理由があり、②社会通念上相当である必要があります。
そこで、それぞれの要件について解説いたします。
(1)要件①について
客観的に合理的な理由があるというのは、労働者の能力不足、義務違反、あるいは経営上の必要性等、解雇を正当化できるだけの理由があるということです。
例えば、仕事は問題なくこなし、他の従業員や顧客からの評判も良いのに、ただ単にあの従業員は気に入らないから解雇する等の単なる好き嫌いが解雇理由の場合、「客観的に合理的な理由」がないということになり、解雇は無効ということになるでしょう。
なお、就業規則のある会社の場合、就業規則において解雇事由を定めることが必要となります(労働基準法89条3号)。
(2)要件②について
仮に、上記要件①を満たしたとしても、我が国の裁判所は、容易に解雇の有効性を認めず、社会通念上の相当性を更なる要件として求めます。
要件②においては、個々の労働者の事情や、解雇の回避が不可能でなかったか等が審査されます。
(3)懲戒解雇の場合
なお、懲戒解雇の場合においても、労働契約法15条では、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」には懲戒処分が無効となるとして、労働契約法16条と同様の文言を用いた定めがなされています。
そして、懲戒解雇は、普通解雇とは性質を異にする制裁罰としての解雇であって、労働者にとっては極刑ともいうべき厳しい処分となるため、普通解雇以上に客観的に合理的な理由や社会通念上の相当性が厳格に判断されます。
2.解雇の理由について
次に、解雇の理由についてみていきたいと思います。
(1)普通解雇の場合
解雇の客観的合理的理由としては、大きく分けて、労働者側に起因する理由と、会社側に起因する理由とに分けられます。
まず、労働者側に起因する理由としては、主に①労働者の能力不足、適格性の喪失(労働者が私的な事故で労働能力を喪失する等)や、②度重なる遅刻等をはじめとした規律違反行為等が挙げられます。
① 労働者の能力不足、適格性の喪失
①の例としては、解雇を有効とした例として、学習塾の講師につき、生徒アンケートの評価が60人以上の講師の中で最下位となることが複数回あり、更に生徒・保護者からのクレームが多数寄せられたこと等を理由とした解雇を有効とした裁判例があります(類設計室事件、大阪地裁平成22年10月29日判決)。
この裁判例では、当該講師の授業内容の改善のための特別模擬授業が複数回行われたにもかかわらず、授業内容が改善向上したとは言えないことも考慮されています。
他方、解雇を無効とした例としては、タクシー運転手として雇用されていた労働者が、運転業務中に二種免許を喪失し(業務上災害との認定はされていません)、解雇の意思表示を受けたものの、二種免許は高度の専門性のある資格とまではいえず、会社側には他の様々な職種もあり、現に当該労働者に清掃職を担当させたりもしていたことから、二種免許の喪失のみをもって解雇することはできないとした裁判例があります(東京エムケイ事件、東京地裁平成20年9月30日判決)。
② 度重なる遅刻等をはじめとした規律違反行為等
②の例としては、解雇を有効とした例として、同僚らに日常的に高圧的、攻撃的な態度を取り、インターネットのサイトで業務と無関係なことをし続けていたりしたことから、解雇の「客観的に合理的な理由」があるとされた裁判例があり(メルセデス・ベンツ・ファイナンス事件、東京地裁平成26年12月9日判決)、他方、解雇を無効とした例としては、ラジオニュースの担当アナウンサーが、2週間において2度寝過ごし、ラジオニュースを一定時間放送できなくさせたのに加え、2回目の放送事故について上司に報告せず、報告を求められた際にも事実と異なる事故報告書を提出したことから会社側から普通解雇された事案で、放送事故につき、事前に当該アナウンサーを起こすべきであったFAX担当者においても寝過ごしていたため、アナウンサーのみを責めるのは酷であること、当該アナウンサーにこれまで放送事故歴がなかったこと等を考慮し、解雇は必ずしも社会的に相当ではないと判断した裁判例があります(高知放送事件、最高裁昭和52年1月31日判決)。
他方、会社側に起因する理由としては、経営上の理由を原因とする解雇であり、このような解雇は整理解雇と呼ばれています。
後者の類型では、労働者側には一切落ち度がないため、解雇の有効性の判断も、労働者側に起因する理由による解雇と比べてより厳格になります。
(2)懲戒解雇の場合
懲戒解雇を含む懲戒処分をする場合には、懲戒事由及び程度を定めておくことが必要であり、定めなしに懲戒処分を行うことはできません(就業規則のある会社の場合、懲戒事由は就業規則で定めることが必要です(労働基準法89条9号))。
また、懲戒事由に書かれていないことを理由として懲戒処分を科すこともできません。
そして、懲戒をすることができる場合における客観的合理的な理由とは、定められた懲戒事由に該当することを前提として、企業秩序を乱す行為、例えば、業務命令違反、無断欠勤等が該当するでしょう。
3.解雇理由の提示について

(1)提示の時期について
会社側は、退職する労働者から、退職の事由について証明書を請求された場合には、遅滞なく交付しなければならず、退職の事由が解雇であれば、その理由まで含めて証明しなければなりません(労働基準法22条1項)。
また、解雇予告された労働者から、解雇日までの間に解雇理由の証明書の交付を請求された場合も同様です(労働基準法22条2項)。
そして、上記のとおり、労働者を解雇するためには、解雇するその時点で解雇(あるいは懲戒)の客観的合理的な理由が必要です。
言い換えれば、労働者の解雇は、解雇のその時点で客観的合理的な理由があるからこそ可能となっているはずであり、労働者から解雇の理由を尋ねられて即答できないというのは本来あり得ないことなのです。
そして、労働者を解雇し、労働者が弁護士にその対応を依頼した場合には、その弁護士から解雇理由についての問合せが来ることになるでしょう。
解雇理由は即答できるはずですので、そのような時に、会社側が2~3週間等長期にわたって解雇理由の回答をしないとなると、解雇時に明確に解雇理由が定まっていなかった、すなわち解雇理由がなかったのではないかと疑われるおそれもあります。
労働審判や訴訟となった場合に、明確な解雇理由を尋ねても長期間回答がなかったと労働者側から主張され、かかる事実を裁判所が会社側に不利に扱うおそれも否定できません。
なお、懲戒解雇の事案において、会社側が訴訟において懲戒解雇の後に判明した事情を解雇理由の一つとして主張したことに対し、懲戒当時に認識していなかった事情をもって懲戒解雇の有効性を基礎づけることはできないとして、会社側の主張を認めなかった判例もあります(山口観光事件、最高裁平成8年9月26日判決)。
したがって、解雇理由については、聞かれたら即答できるぐらいの状態でなければなりません。
(2)提示の方法について
労働基準法22条1項、2項に基づく証明書を労働者側に交付する場合、「就業規則の当該条項の内容及び当該条項に該当するに至った事実関係」を具体的に記載しなければなりません(平成11年1月29日基発第45号)。
すなわち、根拠となった就業規則の条文と、かかる条文に該当することとなった事実関係を具体的に記載する必要があります。
そして、かかる記載が明確にできないとなれば、やはり解雇理由がないと判断されてしまうでしょう。
他方で、証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない(労働基準法22条3項)ので、この点にも注意が必要です。
書式については、厚生労働省のホームページにおいて、モデル書式をダウンロードすることができますが、書式にこだわらず、より詳細な理由を書いた証明書を交付することが望ましいでしょう。
なお、訴訟の段階において、解雇理由証明書に記載されていない事実等、会社側が従前主張していなかったような解雇理由を主張し始めた場合には、やはり解雇理由が定まらないまま解雇したものとみなされ、会社側に不利な判断がなされるおそれが高いでしょう(解雇理由証明書に記載のなかった事由を使用者側において解雇理由として主張することは原則として許されないとした裁判例もあります(広島高裁令和2年2月26日判決))。
4.まとめ
ここまで見てきたとおり、解雇については、法律で非常に厳しく規制されています。
そして、労働者を解雇する場合には、解雇するその時点での明確な理由が必要であり、しかも、理由を聞かれた際には、即答できるぐらいの状態にしておかなければなりません。
労働者の立場からしても、よく分からない理由で解雇され、職を失ってしまうのではたまったものではなく、解雇の理由が不明確な場合には、いざ争いになった場合に使用者側も不利な立場に立たされてしまいます。
そして、会社側があたかも後出しジャンケンのごとく当初の解雇理由と違う理由を後になってから説明し始めたのでは、最初の段階で説明した解雇理由の信憑性も薄れ、最悪の場合には労働審判や訴訟において解雇理由自体がないという判断に至りかねません。
経営者側としては、労働者の解雇を検討せざるを得ない状況になってしまった場合には、可能な限り解雇を回避するよう努め、最後の手段としてどうしても解雇をせざるを得ないと判断した場合には、あらかじめ明確な理由を構成した上で解雇することが必要です。
解雇したい労働者がいるが、そもそも現状考えている理由で解雇が可能なのか、あるいは解雇を回避する方法はあるのか等の場面で悩まれましたら、事前に労働問題に精通した弁護士に相談しておくのが良いでしょう。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
関連記事

パワーハラスメントの6類型とは?パワハラの実態と対処法も解説

スメルハラスメントで労災認定される?認定基準や注意点を解説

パワーハラスメント対策は義務!法改正の内容や対策方法を弁護士が解説






