企業法務のご相談も受付中。お気軽にお問合わせください。
不動産仲介で売渡承諾書に記載する承諾事項とは?売却手続きの進め方・注意点を解説
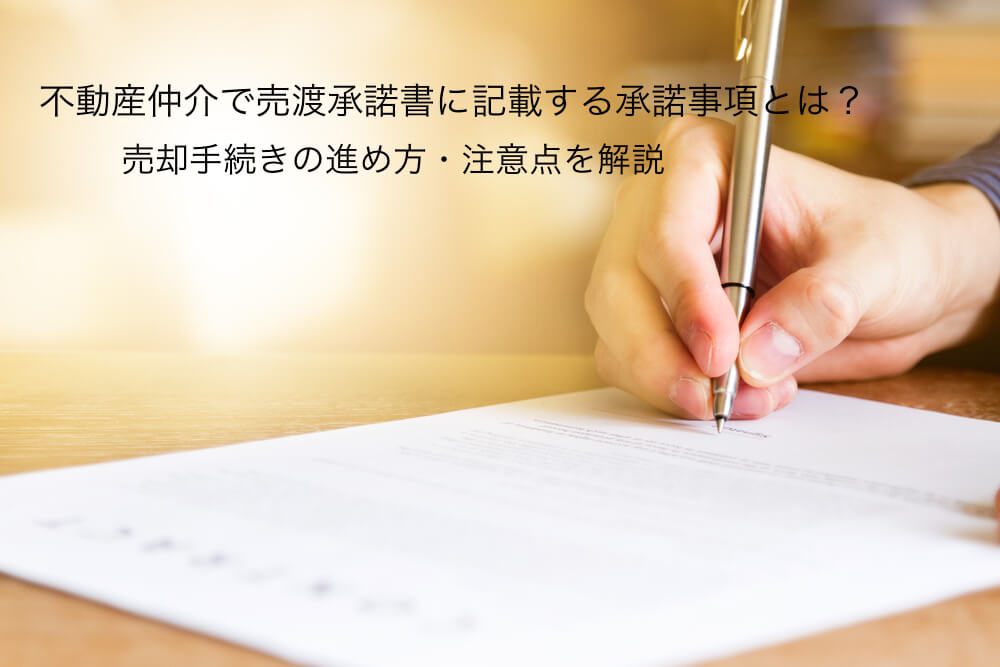
不動産仲介業者に依頼して土地・建物の売買をするときには、不動産会社・売主・買主間でさまざまな書面を交わすのが一般的ですが、そこで重要な役割を担うのが「売渡承諾書」と呼ばれるものです。
取引慣習上、売渡承諾書を交わすことが多いものの、あくまでも「不動産売買契約書」とは異なるため、実務上の位置付けが問題となります。
そこで、今回は、売渡承諾書に記載される承諾事項の内容など、不動産仲介取引で登場する売渡承諾書について解説します。ぜひ最後までご一読ください。
1.不動産仲介で提出する売渡承諾書の承諾事項とは
不動産売買の場面、特に、不動産仲介業者が手続を仲介する際には、売渡承諾書の作成・交付を求められるのが一般的です。
まずは、土地・建物の売渡承諾書の内容について、具体的に見ていきましょう。
(1)不動産仲介の売渡承諾書とは
不動産仲介の売渡承諾書とは、「不動産の購入希望者に対して当該土地・建物を売り渡す意思があること」を旨とする書面のことです。売主から買主に提供されます。
売買契約成立の根拠となる「売買契約書」とは異なり、売渡承諾書は「売却予定者から購入希望者に対する一方的な意思表示」でしかありません。
つまり、売買契約書は「売主・買主の両者の意思が一致したこと」で法的拘束力をもちますが、売渡承諾書にはそれがないということです。
したがって、不動産仲介の売渡承諾書は、原則として法的拘束力を生みだすための役割を担うものではないと考えられます(ただし、一部例外的なケースがあるので、これについては後述します)。
また、売渡承諾書を交付しなくても売却交渉を進めることは可能です。
(2)不動産仲介の売渡承諾書は買付証明書受領後に提出する
売主が購入希望者に対して売渡承諾書を提出するのは、購入希望者から売主に対して「買付証明書」が提供された後です。
- 購入希望者→「買付証明書」→売主
- 売主→「売渡承諾書」→購入希望者
買付証明書とは、「私は当該物件を購入する意思があります」ということを内容とする、購入希望者から売主に対して提供される書面のことです。購入希望者側が考える、買受け希望額やその他条件などが記載されます。
つまり、売渡承諾書は、「『〇〇という条件なら購入します』という購入希望者の意思表示」に対して、「その条件なら前向きに売却を検討します」と呼応する形で提供されるものだといえるでしょう。
なお、売渡承諾書は買付証明書受領後に提出するものであったとしても、あくまでも売買契約書とは異なる性質のものであり、民法上の売買契約の効果を生じない点については変わりありません。
(3)不動産仲介の売渡承諾書の承諾事項とは
それでは、不動産仲介手続きにおいて交付される売渡承諾書の記載内容について具体的に見ていきましょう。
担当する不動産仲介業者や当事者の意向によって記載内容は異なりますが、一般的な承諾事項として挙げられるのは次の通りです。
| 売主・購入希望者の氏名・住所 | 当事者特定のため |
| 売渡承諾書の発行日・有効期限 | 交渉手続きが長期化するのを防ぐ趣旨 |
| 買主に売り渡す意思がある旨 | これを明記しなければ売渡承諾書を交付する意味がない |
| 不動産の特定情報 | 所在地・地目・地積・家屋番号・床面積・構造など |
| 売渡条件 | 販売予定価格や物件の引渡し時期、契約不適合責任の期間、決済日、リフォームや工事の要否など |
もちろん、買付証明書の交付を受けた購入希望者に対して、かならず売渡承諾書を提供しなければいけないというわけではありません。
条件に満たない条件を有する購入希望者を事前にシャットアウトできる点も売渡承諾書のメリットです。
(4)不動産仲介の承諾事項の雛型を紹介
不動産仲介業者に売却依頼をした場合には、業者側が売渡承諾書の雛型を用意してくれます。
業者によって雛形は異なりますが、概ね次のような内容になるのが一般的です。
不動産仲介業者を介せずに不動産を直接売買する場合には、無料のテンプレートとしてご活用ください(エクセルなどで簡単に作成できます)。
| 売渡承諾書
書面発行日 ______殿(購入希望者名を記載) 住所______ 氏名______ 下記不動産を下記条件で売り渡すことを承諾致します。
売却金額 金______万円也とする。
支払い方法 手付金____万円(契約時・現金) 中間金____万円 残代金____万円(決済時・銀行融資)
取引条件 ・現状による引渡しとする ・瑕疵のない完全なる所有権の移転とする ・融資特約や付帯しないものとする ・その他詳細については別途協議とする
有効期限 本書の有効期限は_______までとする。
不動産の表示(登記簿情報) 土地 所在: 地番: 地目: 地積: 建物 所在: 家屋番号: 構造: 延床面積: |
2.不動産仲介で承諾事項の売渡承諾書を提出しても原則法的拘束力はない
不動産仲介の手続き中に交わされる売渡承諾書の実務的な役割・法的位置付けについて、さらに具体的に見ていきましょう。
ここでのポイントは以下3点です。
- 売渡承諾書の実務的な意義は「その後の交渉の円滑化」にある
- 売渡承諾書を提供しても原則法的拘束力は発生しない(実務上、書面交付後も契約内容について交渉が可能なので)
- 売渡承諾書交付後の交渉形態等の事情次第では、例外的に本番の売買契約締結前に契約の拘束力が発生する(一方的な契約関係解消は賠償責任の発生原因になり得る)
(1)不動産仲介の売渡承諾書は交渉を進めやすくするための書面
不動産仲介手続きで売渡承諾書・買付証明書の交付が求められるのは、高額資産である不動産取引を円滑化する趣旨に基づきます。
そもそも、不動産は資産価値が高く、所有するには登記手続きなどを経なければいけないもので、簡単に売買手続きを進められるようなものではありません。
そのような前提を考慮すると、不動産売却を検討している人は「購入に前向きな人を早期に絞って効率的に交渉を進めたい」と考えるでしょうし、不動産購入を検討している人は「他の購入希望者と比較されずに当事者間だけの事情をベースに交渉を進めたい」と希望するのは当然でしょう。
売渡承諾書・買付証明書を交わせば、少なくとも「当事者間で不動産売買に向けて前向きな姿勢であること」が確約します。
双方にとって売却交渉に尽力するのが無駄ではないことが判明すれば、契約交渉が具体化・明確化し、成約に至る可能性も高くなるでしょう。
(2)例外的に売渡承諾書後のキャンセルが賠償責任を生じる場合がある
売渡承諾書・買付証明書は、原則として「交渉手続きを円滑にする」という実務上の役割を担うものであり、売主と購入予定者を特別な法的関係で結び付けるものではありません。
ただし、「売渡承諾書だけでは一切法的拘束力は発生しない」という運用をとった場合、次のようなケースで当事者が不当な不利益を強いられるリスクが生じます。
- 買付証明書・売渡承諾書交付後、既に複数回の交渉を経て契約内容が具体化した段階で、一方当事者が正当な理由なく交渉を打ち切った場合
- 買付証明書・売渡承諾書交付後、契約締結を確約するようなやり取りをしていたのに、一方的に契約締結を反故にした場合
- 売渡承諾書に「購入希望者の同意なく第三者と売却交渉しない」旨の独占的交渉権の記載があったのに、これに反して第三者と交渉し、当該第三者との間で売買契約を締結した場合
このように、買付証明書・売渡承諾書の交付など、当事者間で契約締結に向けて一定の信頼関係が構築されたにもかかわらず、それを事後的に放棄するような事象が発生した場合に、「売渡承諾書だけでは契約の拘束力は発生しない。
したがって、売買契約締結前である以上は一切損害賠償責任を負わない」という主張を正当化してしまうと、売渡承諾書を交わした意味がなくなりますし、不動産仲介取引が不活性化するおそれも生じかねません。
このような形で契約締結を放棄された場合に問題となる事項として、「契約締結上の過失」というものがあります。
もっとも、どの段階に至れば「信義則上の義務」が発生するかという点は、個々の事案によって異なります。
通常、買付証明書や売渡承諾書の交付がされただけでは、契約締結上の過失があるとまでは判断されないと考えられます。
一方、上で挙げたような例外的な事情が存在する場合には、売渡承諾書交付済み・売買契約締結前であったとしても、売買契約が締結されるだろうという相手方の期待を害しないようにする信義則上の義務が生じ、一方当事者は他方当事者に対して損害賠償責任を負う可能性があります。
ただし、契約締結上の過失があるとされた場合の損害賠償責任の範囲は、交渉段階で投下した費用など、契約が締結されるものと信頼したことで発生した費用(いわゆる「信頼利益」)に限られると解するのが一般的です。不動産を手に入れられなかったこと自体に対する賠償は期待できないのでご注意ください。
まとめ
不動産仲介取引で交付が求められる売渡承諾書の承諾事項には法的拘束力はありません。
あくまでも実務上、不動産取引の円滑化を目指すものでしかないので、その後の売却交渉で当事者の意思が合致するように尽力しましょう。
ただし、売渡承諾書を提供した以上、相手方に対して不誠実な対応をとるのは厳禁です。
場合によっては法律問題に発展し、損害賠償責任の負担を強いられるおそれがある点にご注意ください。
このように、不動産という高額資産を取引する以上、売買契約を締結する前の段階から慎重に手続きを進める必要があります。
したがって、不動産の売買を検討する際には、できるだけ不動産仲介業者のような専門業者に依頼をするのがおすすめですし、法的トラブルに発展した場合にはすみやかに弁護士などの専門家のアドバイスを参考にしてください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
関連記事

SES契約により受託した業務はどこまで責任範囲があるのかを解説

不動産買取時に締結する基本契約書とは?売買契約書の意義や雛形を紹介

電子署名の作成方法とは?契約手続き簡素化のポイントを解説






