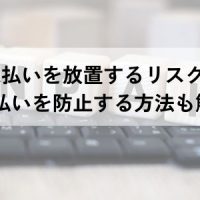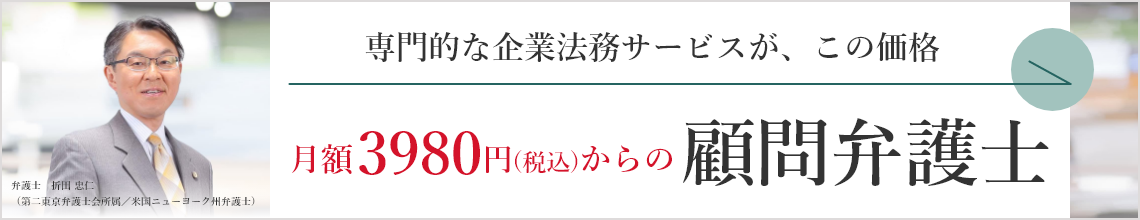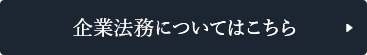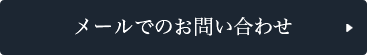企業法務のご相談も受付中。お気軽にお問合わせください。
アルコールハラスメントへの対処法|予防策と事後的な措置を解説

職場の飲み会などでのアルコールハラスメント(アルハラ)は重大な違法行為に該当し、さまざまなトラブルを引き起こすことがあります。
そのため、会社の経営者や人事部門の担当者の方などは、アルハラへの対処法を知り、適切な措置をとることが重要です。
そこで今回は、アルハラ被害を放置した場合に加害者や会社が負うリスクを踏まえて、アルハラ被害が発生してしまった場合の対処法と、アルハラを防止するための対処法について、弁護士が分かりやすく解説します。
1.アルハラ被害が発生したときの対処法
アルハラ被害は未然に防止することが重要ですが、現在の社会状況においては、まだ万全なアルハラ防止対策を講じていない企業も多いのではないでしょうか。
もし、アルハラ被害が発生してしまった場合は、速やかに以下の対処法をとることにより、被害者とのトラブルが深刻化する前に解決することが期待できます。
- 事実の確認
- 被害者への配慮
- 行為者に対する適正な措置
- 損害賠償請求を受けたら示談交渉
- 刑事事件になった場合も示談交渉が重要
- 弁護士への相談
以下で、各項目について具体的にみていきましょう。
(1)事実の確認
まずは、どのような状況で、どのような行為が行われたのか、事実を確認する必要があります。
問題が発生した飲み会に参加した従業員全員から事情を聞くなどして、できる限り正確な状況を把握しましょう。
そして、把握した状況がアルハラに該当するか、該当する場合は悪質性がどの程度なのか、被害者にも落ち度がなかったか(自ら進んで飲酒していたなど)、などを確認していきます。
なお、アルハラとは、法律上の明確な定義はありませんが、一般的には飲酒に関連した嫌がらせや迷惑行為のことを指します。
アルハラに該当する言動には多種多様なものがありますが、典型例として次のようなものが挙げられます。
- 飲酒を強要する
- イッキ飲みをあおる
- 意図的に酔い潰す
- 飲めない人に嫌がらせをする
- 酔った勢いで暴言やセクハラなどの迷惑行為をする
(2)被害者への配慮
アルハラに該当すると判断した場合は、被害者へ配慮するための措置を速やかにとりましょう。
とるべき措置の内容はケースによっても異なりますが、以下のようなことが考えられます。
- 加害者からの謝罪
- 会社としての謝罪
- 職場における配置転換(加害者から引き離すため)
- 治療費の提供
- 休職などの申し出に柔軟に応じる(心身の不調が続く場合)
(3)加害者に対する適正な措置
アルハラは不当な行為なので、加害者に対して適正な措置をとることも必要です。
加害者に対してとるべき措置の内容もケースによって異なりますが、以下のようなことが考えられます。
- 被害者への謝罪
- 職場における配置転換(被害者と引きなすため)
- 懲戒処分(就業規則に該当規定があれば)
(4)損害賠償請求を受けたら示談交渉
アルハラは違法行為なので、被害者から加害者や会社に対して損害賠償を請求されることもあります。
裁判等に発展する前に穏便に解決するためには示談交渉を行い、被害者と誠意をもって話し合うことが大切です。
円満に和解を成立させるためには、適正な賠償金の支払いも必要となります。
賠償金の内訳と適正な金額はケースによって異なりますが、通常は以下の損害項目について検討します。
- 治療費(急性アルコール中毒などで治療を要した場合)
- 休業損害(心身の不調により仕事を休んだ場合)
- 慰謝料
- 逸失利益
逸失利益とは、被害者が将来得られるはずの収入などの利益のことです。
アルハラが原因で被害者がうつ病などの精神疾患を発症して長期的に働けなくなった場合や、死亡した場合に支払いが必要となります。
(5)刑事事件になった場合も示談交渉が重要
アルハラは内容や程度によっては犯罪にも該当する行為なので、被害者が警察に訴えれば刑事事件に発展することもあります。
もし、刑事事件になった場合も、被害者との示談交渉によって穏便な解決を図った方がよいでしょう。
被害者が警察に相談する前に示談が成立すれば、刑事事件化を回避することも可能です。
刑事事件として立件された後でも、速やかに示談を成立させれば「処罰の必要性なし」との理由で不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
被害者が死亡した場合や、後遺障害を負った場合など重大な事案では起訴されることもありますが、示談していれば判決で軽い量刑が期待できます。
(6)弁護士への相談
以上のように、アルハラが発生してしまった場合には法的な対処が重要となることが多いです。そのため、適切に対処するためには早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
企業法務の経験が豊富な弁護士へ相談すれば、以下の点について具体的なアドバイスを受けることができます。
- どのような事実を確認すればよいか
- 被害者に対してどのような配慮をすればよいか
- 加害者に対してどのような措置をとればよいか
- 損害賠償金の相場
- 刑事事件としての処罰の有無や量刑の見通し
- 示談交渉の進め方や交渉のポイント
弁護士に対応を依頼すれば、事実調査から示談交渉まで代行してもらうことが可能です。
その結果、被害者と円満に和解できる可能性が高まります。
刑事事件化した場合も、弁護士が捜査機関へ働きかけたり、刑事裁判で会社側に有利な事情を立証するなどして、不起訴処分や軽い処分の獲得が期待できます。
2.アルハラ被害を放置するリスク
職場の飲み会でアルハラに該当する行為が行われている場合は、早めにアルハラ被害を防止するための措置を講じなければなりません。
アルハラ被害を放置していると、以下のように重大なリスクを負うことに注意しましょう。
- 加害者や会社が損害賠償請求を受ける
- 加害者等が刑事責任を問われる
- 業績が悪化するおそれがある
それぞれのリスクについて、具体的にみていきましょう。
(1)加害者や会社が損害賠償請求を受ける
先ほどもご説明しましたが、アルハラは違法行為なので、加害者や会社が被害者から損害賠償請求を受けることがあります。
アルハラを行った加害者は、民法上の不法行為責任に基づく損害賠償義務を負います(民法第709条、第710条)。
企業は、従業員が安全を確保しつつ働くために必要な配慮をする義務(安全配慮義務)を負っていることから、職場の飲み会でアルハラ被害が発生した場合には、安全配慮義務違反に基づく損害賠償義務を負う可能性が高いです(労働契約法第5条)。
さらに、会社の公式行事としての意味合いが強い飲み会でアルハラ被害が発生した場合には、企業が使用者責任に基づく損害賠償義務を負う可能性もあります(民法第715条第1項)。
損害賠償金の内訳は前記「1(4)」に掲げましたが、被害者が死亡した場合や重大な後遺障害を負った場合には、総額で数千万円から1億円を超える賠償責任が認められることもあります。
(2)加害者等が刑事責任を問われる
アルハラ行為は以下の犯罪に該当する可能性があるので、加害者等が刑事責任を問われて処罰されることもあります。
| 罪名(罰条) | 該当するケース・刑罰 |
| 強要罪
(刑法第223条第1項) |
脅迫または暴行を用いて飲酒を強要した場合。
刑罰は3年以下の拘禁刑。 |
| 傷害罪
(刑法第204条) |
飲酒を強要した結果、被害者が急性アルコール中毒になった場合。
刑罰は15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。 |
| 傷害致死罪
(刑法第205条) |
傷害の結果、被害者が死亡した場合。
刑罰は3年以上の有期拘禁刑(最長30年)。 |
| 過失傷害罪
(刑法第209条) |
意図的に酔い潰したわけではないが、無理にお酒を勧めた相手が急性アルコール中毒になった場合。
刑罰は30万円以下の罰金または科料。 |
| 過失致死罪
(刑法第210条) |
意図的に酔い潰したわけではないが、無理にお酒を勧めた相手が急性アルコール中毒で死亡した場合。
刑罰は50万円以下の罰金。 |
| 保護責任者遺棄等罪
(刑法第218条) |
お酒を勧めた相手が泥酔し、介抱が必要な状態であるのに放置した場合。
刑罰は3か月以上5年以下の拘禁刑。 |
| 保護責任者遺棄等致死傷罪
(刑法第219条) |
介抱が必要な状態の相手を放置した結果、死傷した場合。
刑罰は、致傷の場合は3か月以上15年以下の懲役。 致死の場合は3年以上の有期拘禁刑(最長30年)。 |
| 現場助勢罪
(刑法第206条) |
イッキ飲みをはやし立てるなどして、アルハラ行為に加勢した場合。
刑罰は1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金もしくは科料。 |
酒席での勢いで人にお酒を勧めてしまうこともあるかと思いますが、意外と重罪に問われることもあるので、くれぐれも注意しましょう。
また、自分でアルハラ行為をしなくても、その場の勢いでイッキ飲みをはやし立てたりすると、現場助勢罪に問われることもあるので注意が必要です。
(3)業績が悪化するおそれがある
社内でアルハラが横行していると、お酒が苦手な従業員などは人間関係に苦しみ、モチベーションが低下して業務の効率が落ちるおそれがあります。
アルハラに嫌気がさした従業員が離職するケースも、少なからず見受けられます。
急性アルコール中毒などのアルハラ被害を受けた従業員は、心身の不調が続き、しばらく仕事を休まざるを得ないこともあるでしょう。
さらには、アルハラによる死亡事故などの重大な事案の発生や、会社が損害賠償請求を受けたことなどが明るみに出ると、企業イメージが低下するおそれがあります。
そうなると、顧客や取引先が離れてしまうことにもなりかねません。
このような経緯で、会社の業績が悪化する可能性は十分にあります。
会社の健全な経営を維持するためにも、アルハラ被害を未然に防止する措置を講じておくことは重要です。
3.アルハラが横行している会社で被害を防止するための対処法
アルハラ被害を防止するためには、以下の対処法が有効です。
- 社内ルールの明確化
- 従業員への研修などで周知・啓発
- 相談窓口の設置
それぞれ、具体的にみていきましょう。
(1)社内ルールの明確化
まずは、飲み会における社内ルールを明確に策定しましょう。
ルールの内容は従業員の年齢層や男女比、社風などによって異なることもありますが、一般的には以下の事項を定めておく必要があります。
- 飲酒の強要はしない
- イッキ飲みは禁止
- 飲み会への参加を強制してはならない
- アルハラ加害者に対する懲戒処分などの措置
ルールを決めていても、お酒に酔ってしまうと不適切な言動を始める人も出てくるものです。
その場合の対処法も決めておきましょう。
例えば、飲み会ごとにアルハラ防止の担当者を決めることとし、不適切な言動を始めた従業員に対しては、担当者から飲酒の中止や退席などの指導をすることが考えられます。
また、万が一、アルハラが発生したときの対処法もルール化しておくべきです。
具体的には、前記「1」でご紹介した対処法を円滑に実行できるように、担当者を決めたり、社内の仕組みを構築したりすることになるでしょう。
(2)従業員への研修などで周知・啓発
アルハラ防止の社内ルールを策定したら、その内容を全従業員へ周知・啓発する必要があります。
アルハラを禁止する旨の方針や、懲戒処分などの重要事項については、就業規則に規定を設けて従業員に対して注意を促すべきです。
その上で、従業員を対象とした研修を実施し、主に次のようなことをわかりやすく説明して、従業員の理解を深めるようにしましょう。
- どのような言動がアルハラに該当するのか
- 飲み会の席で具体的に注意すべきこと
- アルハラに遭遇したときにやるべきこと
(3)相談窓口の設置
アルハラは経営陣の気づかないところで行われることが多いため、重大なトラブルを回避するためには早期にアルハラ問題を把握し、適切に対処することが極めて重要です。
そのために、アルハラの被害者や目撃者などが気軽に相談できる窓口を社内に設置しましょう。
相談窓口としては、専用の部署を設ける必要はなく、担当者をあらかじめ定めておくだけでも構いません。
ただし、担当者が相談の内容や状況に応じて適切に対応できるように、人事部門と連携を図れる仕組みを作ったり、対応方法をまとめたマニュアルを作成したり、対応スキルを高めるための研修を実施したりすることも必要です。
従業員には、気軽に相談できる窓口がある旨と、担当者の連絡先、相談したことを理由として不利益な取り扱いを受けることはない旨を周知しましょう。
4.顧問弁護士を依頼するならベリーベストがおすすめ
アルハラによるトラブルが発生した場合は、弁護士への相談・依頼が最も有効な解決方法となります。
とはいえ、社内のアルハラ問題で弁護士に相談することには気恥ずかしさもあり、躊躇してしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、日ごろから社内の実情を熟知している顧問弁護士がいれば、このような内容でも気軽に相談することが可能です。
そもそも顧問弁護士がいれば、あらゆる観点から会社にとってのリスクを回避するためのアドバイスが得られるので、アルハラ問題の発生防止にも大きく役立ちます。
顧問弁護士を依頼するなら、豊富な実績を有するベリーベスト法律事務所へのご相談をおすすめします。
当事務所は全国に75か所の拠点を有し(2024年7月時点)、約360名の弁護士が所属しておりますので(2024年2月時点)、全国どこでも速やかな対応が可能です。
ちょっとしたお困りごとや、外部には相談しにくい問題についても、担当弁護士へお気軽にご相談いただけます。
困難なトラブルが発生した場合には、各分野ごとに構成された専門チームに所属する弁護士と連携して対応しますので、適切な解決が期待できます。
顧問料につきましては、3980円から選べる豊富なプランをご用意していますので、費用の負担が気になる方もお気軽にご相談いただけます。
アルハラ問題でお困りの方も、アルハラ問題の予防策をお考えの方も、一度、当事務所へご相談ください。
まとめ
アルハラは、被害者に心身の健康上のリスクをもたらすだけでなく、加害者や企業にも法的責任や業績の悪化などのリスクが及びかねない重大な問題です。
アルハラが社会問題化しつつある昨今において、企業としてはアルハラを防止するための万全な対策をとった上で、実際にアルハラが発生した場合には迅速かつ適切に対応する必要があります。
顧問弁護士の契約をしていれば、社内の実情を熟知した弁護士からの丁寧なアドバイスが期待できます。アルハラ問題の防止やトラブル解決にも大きく役立つはずです。
顧問弁護士へのご依頼をお考えの方は、ベリーベスト法律事務所へお気軽にご相談ください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
関連記事
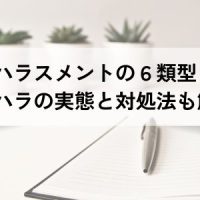
パワーハラスメントの6類型とは?パワハラの実態と対処法も解説
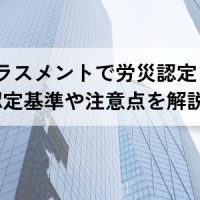
スメルハラスメントで労災認定される?認定基準や注意点を解説
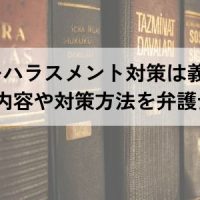
パワーハラスメント対策は義務!法改正の内容や対策方法を弁護士が解説