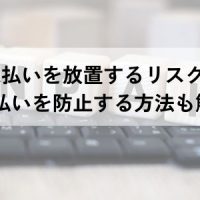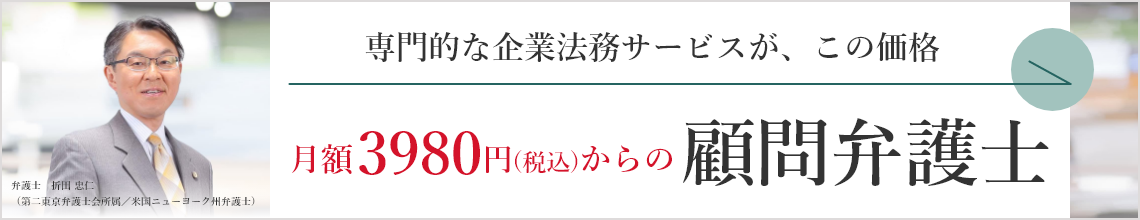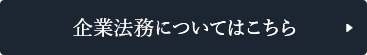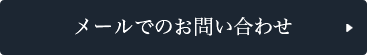企業法務のご相談も受付中。お気軽にお問合わせください。
パワーハラスメント対策は義務!法改正の内容や対策方法を弁護士が解説
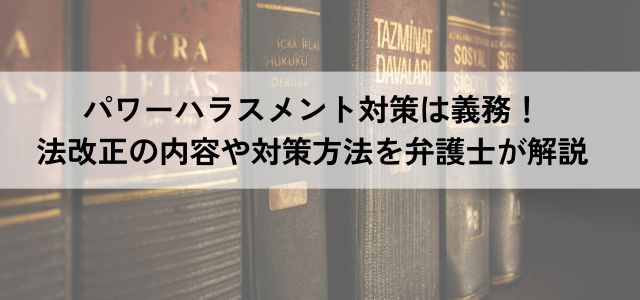
パワーハラスメント(パワハラ)が社会問題化している状況において、法改正により2022年4月から、中小企業を含むすべての企業において、パワハラを防止するための対策をとるべきことが義務化されました。
とはいえ、具体的に何をすればよいのかがわからず、実効的なパワハラ対策を構築できていない企業もあるのではないでしょうか。
そこで今回は、パワハラ対策が義務化された法改正の内容を踏まえて、企業の実態に合ったパワハラ対策を講じる方法について、企業法務の経験が豊富な弁護士が解説します。
1.企業の実態に合ったパワハラ対策を講じる方法
パワハラ対策の内容は、自社の実態に合ったものにすることが重要です。
なぜなら、パワハラ行為には多種多様なものがあり、どのようなパワハラが発生しやすいかは企業ごとに異なるからです。
ある程度は業種ごとに共通する傾向もありますが、会社の規模や従業員の年齢層、各従業員の性格などにより、実態は個々に異なります。
企業の実態に合ったパワハラ対策を講じるためには、以下の3つのステップを踏んで作業を進めていくことをおすすめします。
- 社内アンケート等で実態を把握する
- 厚生労働省の「パワーハラスメント対策導入マニュアル」を参照する
- 弁護士からアドバイスを受ける
(1)社内アンケート等で実態を把握する
まずは、自社の実態を把握する必要があります。そのためには、社内アンケート等で従業員の生の意見を集めることが有効です。
従業員の本音を把握するためには、匿名(無記名)でのアンケートを実施するのがよいでしょう。
具体的には、パワハラとは何かを明確に示した上で、次のような事項について回答を求めます。
- パワハラを受けたことがあるか
- 上司や同僚の言動が「パワハラではないか」と感じたことがあるか
- 他の従業員がパワハラを受けていることを見聞きしたことがあるか
- 上記の各項目について、「ある」と回答した場合は言動の具体的内容
アンケートの段階では、厳密にパワハラに該当する事例のみの回答を求めるのではなく、身体的または精神的な苦痛を感じた言動の事例について、広く回答を求めるようにしましょう。
従業員が苦痛に感じている事例を幅広く集めた方が、自社の実態をありのままに把握しやすくなるからです。
各事例がパワハラに該当するかどうかの判断は、次のステップで行います。
(2)厚生労働省の「パワーハラスメント対策導入マニュアル」を参照する
自社の実態を把握したら具体的なパワハラ対策を検討していくことになりますが、その際には、厚生労働省が策定した「パワーハラスメント対策導入マニュアル」を参照するのがおすすめです。
パワーハラスメント対策導入マニュアルとは、各企業において効果的なパワハラ対策を構築できるようにするため、その進め方や参考となる情報等を厚生労働省が取りまとめて公表した冊子のことです。
このマニュアルでは、以下のことがわかりやすく説明されています。
- パワハラとは何か
- パワハラの具体例や裁判例
- パワハラ対策を構築する手順
- パワハラ対策への取り組みを継続するためのポイント
ボリュームはありますが、このマニュアルに沿って作業を進めていけば、基本的なパワハラ対策は構築できるようになっています。早めに一度、目を通しておくとよいでしょう。
(3)弁護士からアドバイスを受ける
パワーハラスメント対策導入マニュアルは、あくまでも一般論をまとめたものに過ぎません。
企業の実態に合ったパワハラ対策を構築するためには、このマニュアルを参照しつつも、「自社における状況はどうか」、「自社ではどのように対処すればよいか」といった個別的かつ具体的な検討を要します。
この段階では、弁護士に相談して専門的なアドバイスを受けるのがおすすめです。
企業法務の経験が豊富な弁護士へ相談すれば、自社の実態を踏まえた実効的なパワハラ対策を構築するための丁寧なアドバイスが期待できます。
2.企業にパワーハラスメント対策が義務化された背景
企業にパワーハラスメント対策が義務化された背景として、職場におけるパワハラが社会問題化し、パワハラを防止すべきという社会的な機運が高まったことが挙げられます。
パワハラに該当するケースは、以前から少なからず発生していました。しかし、近年では人権意識の高まりもあり、上司の威圧的な態度や同僚からの嫌がらせなどに悩んでいた労働者が声を上げるようになってきたと考えられます。
重大な事案では、被害者が慰謝料などを求めて加害者や会社に対して訴訟を提起し、被害者が勝訴するケースも増えてきました。
国もこのような事態を重要視し、労働者が能力を有効に発揮できる職場環境を維持できるようにするため、法改正に乗り出したのです。
具体的には、労働施策総合推進法を改正し、パワハラに対して事業主が講ずべき措置等に関する規定を盛り込みました(同法第9章)。
改正された労働施策総合推進法は俗に「パワハラ防止法」とも呼ばれ、2020年6月から大企業を対象として、2022年4月からは中小企業も含めた全企業を対象として、施行されています。
3.法改正で義務付けられたパワハラ対策の内容
改正労働施策総合推進法では、事業主は職場におけるパワハラを防止するために、労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備し、その他の雇用管理上必要な措置を講じることを義務づけられています(同法第30条の2第1項)。
ただし、具体的にどのような措置を講ずべきかについての指針は、厚生労働大臣が定めるものとされました(同条第3項)。
この規定に基づき、厚生労働省は2020年6月、いわゆる「パワハラ防止指針」を策定して公表しました。
パワハラ防止指針では、事業主が講ずべきパワハラ対策の内容として以下の4項目が掲げられています。
- 社内方針の明確化と周知・啓発
- 相談に適切に対応できる体制の整備
- パワハラが発生した場合の迅速かつ適切な対応
- 併せて講ずべき措置
それぞれについて、具体的にみていきましょう。
(1)社内方針の明確化と周知・啓発
まずは、職場におけるパワハラは会社として許さないという方針を明確化し、打ち出す必要があります。
打ち出した社内方針に実効性を持たせるためには、パワハラの内容や、パワハラを行った者に対する懲戒処分などの対処方法などを明確に定めることも必要です。
以上のことを明確化したら、管理監督者を含む全従業員に対して周知・啓発します。
その方法としては以下のものが挙げられますが、できる限り、すべて行うことが望ましいです。
- 就業規則等の文書に必要な規定を盛り込み、注意喚起する
- 社内報やパンフレット、ポスター、社内ホームページなどに掲載し、配布・配信する
- 従業員を対象とした研修や講習を実施する
(2)相談に適切に対応できる体制の整備
パワハラは経営陣が気づきにくいところで行われることが多いため、苦痛を感じた従業員が気軽に相談できる窓口をあらかじめ定め、従業員に周知する必要があります。
相談窓口を定める際には、必ずしも専用の部署を設ける必要はなく、以下の方法でも構いません。
- 相談に対応する担当者を定めておく
- 相談に対応するための制度を設けておく
- 相談への対応を外部に委託する
そして、従業員からの相談内容や状況に応じて、相談窓口の担当者等が適切に対応できるようにしておくことも必要です。
具体的には、次のような体制の整備が考えられます。
- 相談窓口の担当者と人事部門が連携を図れる仕組みを作っておく
- 留意点などをまとめた対応マニュアルをあらかじめ作成しておく
- 相談窓口の担当者を対象として、相談への対応方法についての研修を実施する
(3)パワハラが発生した場合の迅速かつ適切な対応
パワハラを防止するための措置を講じたとしても、パワハラが発生してしまう可能性は十分にあります。
そのため、パワハラが発生した場合の事後的な対応についても、迅速かつ適切に行えるように定めておくことが必要です。
具体的には、以下の4つの措置について、社内の実情に応じて具体的な内容や手順を定めておきましょう。
- 事実関係を迅速かつ正確に確認する
- 被害者に対する配慮のための措置(配置転換やメンタル面のケアなど)を速やかに、かつ適正に行う
- パワハラの事実が確認できた場合は、加害者に対する措置(懲戒処分など)を適正に行う
- 再発防止に向けた措置を講ずる(再度の研修、講習など)
(4)併せて講ずべき措置
上記(1)~(3)の措置を講ずる際には、プライバシーの侵害や、雇用関係における不利益な取り扱いなどの二次被害が生じるおそれもあります。
そのため、事業主は以下の措置を合わせて講じなければなりません。
- 被害者、加害者、関係者のプライバシーを保護するために必要な措置を講ずるとともに、その旨を従業員に対して周知すること
- 相談したことや、相談への対応に協力して事実を述べたことなどを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしないことを定め、その旨を従業員に対して周知・啓発する
4.パワハラ対策が不十分な場合に生じるリスク
企業の実態に合ったパワハラ対策を万全に構築しようとすれば、さまざまなことを考えなければならないため、難しく感じることもあるでしょう。
しかし、パワハラ対策が不十分なまま放置すると、以下のようなリスクを抱えることになります。
- 業績悪化のおそれがある
- 刑事罰はないが企業名を公表されることがある
- 従業員から損害賠償を請求されることがある
どれも、企業にとって見逃せないリスクばかりです。以下で、それぞれのリスクについて具体的にみていきましょう。
(1)業績悪化のおそれがある
パワハラを受けた従業員は精神的にダメージを受けるため、通常は仕事へのモチベーションが低下してしまいます。
重大な被害を受けた場合には、退職に至るケースも少なくありません。
パワハラが横行しているような職場では、離職者が相次ぐことも考えられます。
その事実がSNSなどで明るみに出ると企業イメージが低下してしまい、新卒者の採用に支障をきたすこともあるでしょう。
このようにして人手が不足すると生産性が落ち、企業の業績が悪化するおそれがあります。
(2)刑事罰はないが企業名を公表されることがある
労働施策総合推進法には罰則がないため、パワハラ防止措置を講じなくても刑事罰を科せられることはありません。
しかし、法の規定を遵守しなければ、厚生労働大臣から助言や指導、勧告を受けることがあり(同法第33条第1項)、勧告に従わなかった場合には企業名を公表される可能性があります(同条第2項)。
もし、重大なパワハラ問題が発生した企業として公表されてしまうと、企業イメージが著しく低下して、業績が大幅に悪化するおそれもあるでしょう。
(3)従業員から損害賠償を請求されることがある
パワハラに刑事罰はなくても、従業員から損害賠償請求される可能性があることに注意が必要です。
パワハラは民事上違法な行為であり、加害者は、民法上の不法行為に基づく損害賠償義務を負います(同法第709条、第710条)。
会社が十分なパワハラ対策を講じていなかった場合には、事業主も使用者責任(民法第715条第1項)あるいは安全配慮義務違反(労働契約法第5条)に基づく損害賠償義務を負う可能性が高いです。
パワハラによる慰謝料は、認められても数万円~数十万円のことが多いです。
しかし、被害者がうつ病などの精神疾患を発症して働けなくなったような場合には、高額の損害賠償を命じられることもあります。
それだけでなく、会社が訴えられた事実や敗訴したことが報道されるなどして明るみに出ると、企業イメージが低下して業績悪化につながるおそれがあることも見過ごせません。
このように、従業員から損害賠償請求をされると、会社が経済的ダメージを負うリスクがあることにも注意しておく必要があるでしょう。
まとめ
パワーハラスメント対策を講ずることは、改正労働施策総合推進法に基づく事業主の義務です。
十分な対策を講じないまま重大なパワハラが発生すると、業績が悪化するなどして企業の存続が危ぶまれることにもなりかねません。
企業が健全な経営を継続するためにも、従業員が働きやすい職場環境を維持することは重要です。
そのためには、企業の実態に合ったパワハラ対策を万全に構築しておく必要があります。
パワハラ対策の構築でお悩みの際は、企業法務の経験が豊富な弁護士へのご相談を強くおすすめします。
自社に特有のリスクにも配慮した、効果的なパワハラ対策を構築できるようになることでしょう。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
関連記事
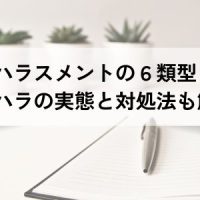
パワーハラスメントの6類型とは?パワハラの実態と対処法も解説
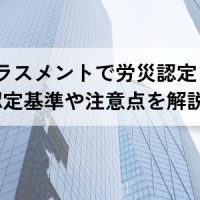
スメルハラスメントで労災認定される?認定基準や注意点を解説
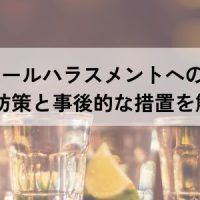
アルコールハラスメントへの対処法|予防策と事後的な措置を解説