企業法務のご相談も受付中。お気軽にお問合わせください。
契約書作成の基礎 (2)債務不履行に伴う責任とは

1. はじめに
今回は、債務不履行に伴って生じる解除、損害賠償の条項を中心に説明をしていきたいと思います。
特に、2020年4月1日から施行されました改正民法により影響が生じやすそうな内容を中心に説明いたします。
2. 解除

(1)民法改正により検討すべき事項
民法改正により、解除の要件は大幅に変更されています。
解除制度は契約関係から債権者を離脱させるための制度に位置付けが変更されたため、解除の要件として債務者の帰責事由が不要とされました。
もっとも、債務不履行が軽微な場合には解除ができないと改正されたことから、何が軽微な不履行か、当事者双方でトラブルになる可能性があります。
そこで、契約書において、解除事由を明確に定めることが大切です。
(2)解除事由の具体例
契約の内容によって、個別具体的にどういった事由を解除事由とすべきか検討が必要ですが、例えば以下のような事由が挙げられます。
あくまでも個々のケースで解除事由は検討が必要です。
①相手方の信用力に問題があることを伺わせる事情
EX)
- 手形、小切手の不渡りとなったとき
- 監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき
- 第三者から強制執行の申立てをされたとき
- 公訴公課の滞納処分を受けたとき
- 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算手続が開始されたとき
- 解散、合併、会社分割、事業譲渡の決議をしたとき
※合併、会社分割、事業譲渡は、親会社の経営の効率化等を図るために経営判断によるものであるケースもあるため、常に信用力に問題があることを伺わせる事情ではありません。
そのため、子会社の立場にある会社は、将来的に組織再編がなされる可能性があることを想定して、敢えて合併等を解除事由から外すということも検討すべきでしょう。
一方、相手方は、自社の競合他社などと合併したり、事業譲渡されたりする場合には取引の継続を検討する機会(解除権)を確保したいと考えるでしょう。
②各契約において特に解除事由として定めるべき事項
ある事象が発生した場合に契約を解消したいと想定する場合には、ビジネスごとに具体的な解除事由を定めておいた方がよいでしょう。
そうしなければ、解除することができるかについて、紛争化し、訴訟に発展する可能性があります。
以下では、具体的なケースを想定した上で、どういった解除事由が必要か考えていきましょう。
ア 請負契約における目的物設置義務
商品の売主がある場所に目的物を設置するという請負の性質を有した付随的な債務を負っているケースを想定します。
設置する債務が誰でも容易なものであれば、債務不履行が軽微かどうか解釈をめぐってトラブルになる可能性があります。
そのため、売主の目的物を設置するという債務が解除事由になることは契約書に明記しておくべきでしょう。
イ 製造物供給契約における製品の仕様書との不一致
製造物供給契約において、製造された物が当初想定された仕様と異なっていたケースを想定します。
仕様と異なっていたとしても、製造物を使用する用途において何ら問題がないものであれば、当該債務不履行は軽微と評価され得る可能性もあります。
委託者は、受託者と協議し、製造物の仕様書を作成した上で、仕様書のうちどの箇所が異なっていれば解除可能なのか定めておくべきでしょう。
他方、受託者の側は,委託者が作成した仕様書の内容を細かくチェックする必要があります。
委託者は、仕様書に詳細な条件を盛り込み、その条件が契約の内容の含まれるものとして、条件に抵触する場合には、解除、製造物の修正等を求めてくることがあります。
そのため、受託者は、仕様書の内容の中に遵守が困難な事項がないか確認し、困難な内容が含まれていれば、交渉の上、訂正を求めるべきです。
ウ 不動産賃貸借契約における賃料の滞納
不動産の賃貸借契約において、借主が1か月分の賃料を滞納したケースを想定します。
賃貸借契約においては、特別の配慮が必要となります。
判例によれば、賃貸借契約においては、信頼関係が破壊されたといえる事情がなければ、解除ができないとされています。
そのため、賃料の滞納金額が1か月あった場合に解除ができるという定めが契約書に明記されていたとしても、貸主は当然に解除ができる訳ではありません。
契約書における解除事由は、賃料の滞納金額が3か月以上の金額に達したときなどにしておいた方が穏当でしょう。
もっとも、賃料の滞納金額が1か月の場合であっても、騒音で近隣住民に迷惑をかけていたり、ゴミ屋敷にしていたりといった事情があれば、信頼関係が破壊されているとして、解除が可能となるケースもあります。
様々なケースを想定して解除事由を定めることが望ましいでしょう。
ただし、上記のとおり、解除事由を具体的に定めたとしても、信頼関係が破壊されていなければ解除ができないため、貸主は、安易に解除をせず、まずは弁護士に相談すべきです。
エ ブランド商品の売買契約におけるブランド価値維持義務
ブランディングの一環として、詳細なルールを定め、当該ルールに違反したことを解除事由にすることがあります。
例えば、ブランド商品を販売する企業は、ブランド力を保持するために、HP等における宣伝の方法、商品のロゴの使用方法、企業のイメージを棄損する可能性のある行為の禁止等詳細なルールを定めることがあります。
ブランディングを考えている企業は、契約書において、詳細なルールを設定し、ブランド力の強化を図った方がよいでしょう。
このように、契約書は、経営戦略的に非常に重要な役割を果たすこともあります。
3. 損害賠償
売買契約について、特に民法改正によって、(1)瑕疵担保責任が契約不適合責任となったこと、(2)債務の履行に代わる損害賠償の要件が具体化されたこと、の2点につき考慮が必要になります。更に、(3)損害賠償額の立証の負担や交渉を避けるため違約金条項についても考慮が必要です。
(1)契約不適合責任(改正民法563条、564条、415条)
旧民法においては、瑕疵担保責任によって、損害賠償請求が認められるためには、売主に帰責事由は不要でしたが、認められる損害は信頼利益に限定されていました。民法改正により、瑕疵担保責任が契約不適合責任となったため、売主に帰責事由が必要となり、損害は履行利益まで認められることとなりました。
他方、売主に帰責事由がない場合には買主は契約不適合責任に基づいては損害賠償請求ができないため、売主に金銭を請求しようと思うのであれば、履行の追完の催告をした後に、代金の減額を請求することとなります。
これらの改正内容をふまえて、契約で民法の規律を修正していくか、検討していくことが必要となります。
(2)債務の履行に代わる損害賠償(改正民法415条第2項)
民法改正により、以下の場合には債務の履行に代わる損害賠償をすることができるものとされました。
①債務の履行が不能であるとき
②債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき
③債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき
特に問題となりやすい点は、②の債務者が履行を「拒絶する意思を明確に表示したか」とはどういった場合を指すのかという点です。
例えば、債務者が債権者に対し履行をしない旨の文書を送付したときは、債務の履行に代わる損害賠償ができるといったように具体的な定めを置くことがよいでしょう。
(3)違約金の定め
旧民法420条第1項後段は、当事者が損害賠償額の予定を合意した場合には、裁判所は当該予定額を増減することができないと定めていました。
しかし、実務的には、公序良俗違反(民法90条)を根拠として、過大と認められる部分の効力は否定されてきました。そこで、改正民法においては、旧民法420条第1項後段の定めは削除されました。
民法420条第3項は、違約金が違約罰ではなく損害賠償額の予定と推定するものと定めております。
それに対して、違約罰は、違約金と異なり、損害の発生の有無に関わらず支払うものであるため、損害が発生した場合には別途損害賠償義務が発生します。
損害賠償に関して、一般的な問題として、損害額がいくらであるのか立証することが難しいケースが多いです。
債務不履行が発生した場合には、例えば、「違約金として金100万円を支払う」といった条項を盛り込むことも検討してもよいでしょう。
更に、実際の損害の金額が違約金の金額100万円を超えるケースもあるため、損害額が違約金額100万円を超える場合については、違約金と損害額の差額を請求することができるという内容の条項を明記しておくことが無難です。
他方、債務を負う当事者は、当該条項があれば、損害額の評価をめぐってトラブルになることを避けられないため、損害賠償額の予定として違約金の規定を設け、違約金以上の金額を支払うことがないよう交渉していくべきでしょう。
4. まとめ
民法改正により、解除の要件や損害賠償について、契約書の内容を修正すべきか検討が必要です。
また、賃貸借契約など一定の契約は、判例法理が契約書の定めに優先します。
これまでの契約書をそのまま使用している企業は、今一度,契約書を修正する必要がないか、自社で研究すると共に、弁護士に相談し最終チェックをされた方がよいでしょう。
その他にも、ブランディング戦略、特許戦略などの知財戦略その他の経営戦略の観点および契約の相手方の戦略や業界でのポジションなどから、詳細なルールを定めるべきこともあります。
単純に、法的なリスクを防止するという観点だけではなく、様々な視点から、契約書は作成されるべきです。

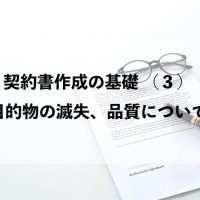

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
関連記事

SES契約により受託した業務はどこまで責任範囲があるのかを解説

不動産仲介で売渡承諾書に記載する承諾事項とは?売却手続きの進め方・注意点を解説

不動産買取時に締結する基本契約書とは?売買契約書の意義や雛形を紹介






