企業法務のご相談も受付中。お気軽にお問合わせください。
業務委託により労働力を確保する際の労働基準法を中心とした注意点①
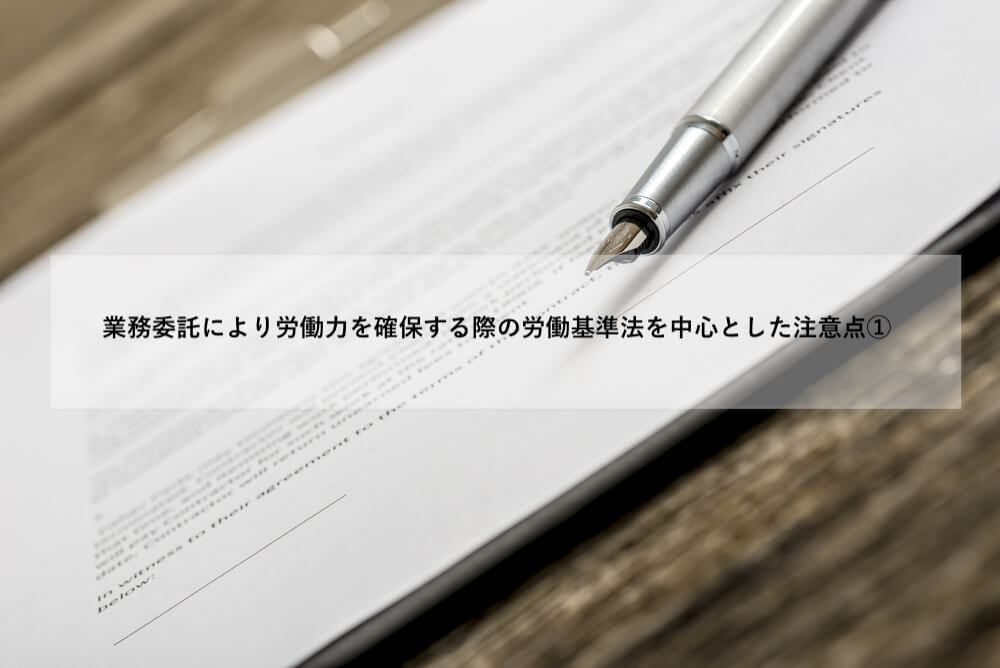
近年、雇用類似の働き方、あるいは、雇用関係によらない働き方が注目を浴びています。
このような中、「雇用」という方式をとらず、「業務委託」や「請負」、「準委任」という形式で個人に業務の一部を外注する企業も多いかと思われます。
しかし、このように、「業務委託」等の形式で個人に外注をした場合でも、その実態によっては労働基準法等が適用される可能性があることはご存じでしょうか。
また、労働基準法等が適用されなかったとしても、別の規制が存在します。
本稿では、労働基準法等が適用された場合のデメリットや、労働基準法等の適用基準と労働基準法が適用されないための対応策、労働基準法等が適用を回避されなかった場合の注意点について解説します。
1.労働基準法等が適用された場合のデメリット
日本には、労働契約法や労働基準法、労働者災害補償保険法、労働組合法、労働関係調整法、労働安全衛生法、男女雇用機会均等法、雇用保険法、最低賃金法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法)など多数の労働に関係する法律があります。
そして、労働基準法が適用されるケースでは、他の数多くの法律も一緒に適用されることが多いです。
これは、後に解説しますが、労働基準法をはじめ、多くの労働法は、「労働者」に適用されることとなっており、「労働者」という概念が多くの法律で共通しているためです。
以下では、労働契約法、労働基準法、労働者災害補償保険法、労働者派遣法に限定して、それぞれの法律が適用された場合のデメリットについて説明します。
(1)労働契約法が適用された場合
業務委託先等が「労働者」と認められる場合には、業務委託先等との契約関係を解消することは、雇用契約を解消すること、つまり、解雇と同様に扱われることとなります。
そのため、業務委託先等との契約関係を解消したいと考えても、解雇の場合と同様に、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」に該当しないことという厳しい要件を満たす必要があります(労働契約法16条)。
また、業務委託契約に契約期間が定められていることも多いと思いますが、契約期間が定められた業務委託契約の更新をしたくないと考えた場合でも、契約更新が合理的に期待できる状況にあるときには、契約の更新の拒絶にも、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき」に該当しないことが必要となります(労働契約法19条2号)。
さらに、5年間以上契約を更新してきた場合には、その業務委託先等からの求めがあるときには、その業務委託先を無期の労働者として扱う必要があります(労働契約法18条1項)。
仮に、業務委託先等との契約関係を一方的に解消した場合には、業務委託先等から、訴訟を起こされる可能性があります。
そして、裁判官が、業務委託に労働契約法が適用され、解雇(更新拒絶)が無効であるという判決を下した場合には、契約解消(解雇)や更新拒絶以降の業務委託費(賃金)も支払わなければなりません。
このように、労働契約法が適用された場合、業務委託先との契約を解消することが困難となってしまいます。
(2)労働基準法が適用された場合
労働基準法が適用された場合の制限として、特に重大なものは、業務委託先等が業務をすることのできる時間に1日8時間、1週間に40時間という制限がかかり(労働基準法32条)、その結果、制限を超えて業務をさせた場合には割増賃金を支払う必要があるという点でしょう(労働基準法37条1項)。
その他、解雇予告制度(労働基準法20条)や有給休暇制度(労働基準法39条)の適用があることや、違約金の定めが無効となること(労働基準法16条)、期間の定めのない場合を除き契約期間は3年を超えることができず(労働基準法14条)、1年以上の契約期間を定めたとしても、1年以上経過した場合は、いつでも契約を解消(退職)されてしまうこと(労働基準法137条)にも注意をすべきです。
なお、労働時間や割増賃金の支払い、解雇予告制度、有給休暇制度など、労働基準法の規定に違反した場合には、刑事罰が科せられる可能性があります(労働基準法117条乃至121条)。
(3)労働者災害補償保険法が適用された場合
業務中や出退勤中にケガをした業務委託先等が「労働者」といえる場合には、各種届出や保険料の支払いが未了であったとしても、労働者である業務委託先等は、労災の申請を単独で行うことができます。
そして、労働基準監督署が、業務委託先等を「労働者」と認め、労災保険給付をした場合には、事業主は、労災保険料を2年分払わなければいけないほか、追徴金を支払わなければなりません(労働保険の保険料の徴収等に関する法律21条1項、41条)。
また、労災に未加入であったことについて、企業側に故意・重大な過失があった場合には、労災事故について企業側に安全配慮義務違反がなかったとしても、労災保険給付の一部または全部を企業側が支払う必要があります(労働者災害補償保険法31条1項1号)。
(4)労働者派遣法が適用された場合
企業に対して業務を委託した場合においても、注意が必要です。
例えば、A社がB社にA社内で特定の業務(プログラミング等)を行う人員の派遣を委託し、B社がB社の従業員CをA社に派遣したとします。
このとき、A社が、Cを「指揮監督していた」といえる場合には、Bが労働者派遣事業の許可を受けていなければ、ABC間の関係は、違法な労働者派遣に該当してしまいます。
そして、Aが違法な労働者派遣に該当することを知っていたか、あるいは、知らないことに過失があった場合には、Aは、BC間の雇用契約と同一の条件で、Cに対して、雇用契約の申し込みをしたものと擬制され、この申し込みの効力は、違法状態の解消から、1年間有効とされてしまいます(労働者派遣法40条の6第1項、第2項)。
そのため、CがA社との雇用関係を望んだ場合には、A社で雇用をする必要が生じます。
また、罰則規定もあります(労働者派遣法59条等)。
そして、このことは、BC間の契約が業務委託という名目であったとしても、実態として、CがAに派遣されるB社の「労働者」と評価され、CをAが指揮監督していれば、同様の現象が起こり得ることに注意が必要です。
2.労働基準法等が適用される基準と対応策

(1)労働基準法等が適用される基準
前記1.のとおり、労働基準法等が適用されるかは、業務委託先等が、労働基準法上の「労働者」に該当するか否かにより決まります。
労働基準法上の「労働者」とは、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」(労働基準法9条)と定義されています。
そして、業務委託先等が労働基準法上の労働者に該当した場合には、労働安全衛生法(同法2条2号)、最低賃金法(同法2条1号)における「労働者」にも該当することになるため、労働安全衛生法と最低賃金法も適用されます。
また、労働基準法上の労働者といえる場合には、労働者災害補償保険法や、労働契約法上の「労働者」にも該当し、労働者災害補償保険法や労働契約法が適用されると考えられています(平成23年厚生労働省「労使関係法研究会報告書(労働組合法上の労働者性の判断基準について)」)。
また、労働基準法上の「労働者」とは異なる概念として、労働組合法上の「労働者」という概念もあります。
労働組合法上の「労働者」とは、「職業の種類を問わず、賃金、給料、その他これに準ずる収入によって生活する者をいう」(労働組合法3条)とされており、労働基準法が適用されなくても労働組合法は適用されるというケースが多数存在します。
近年では、AがBに業務を委託し、BがCを雇用したという事例において、AC間への労働基準法等の適用を否定した裁判所の判決(札幌地判平30.9.28労判1188号5頁)の後に、北海道労働委員会が、平成31年4月26日、AC間での労働組合法の適用を肯定し、救済命令を出したことが注目されます。
労働基準法、労働組合法の「労働者」に該当するかの具体的な考慮要素については、昭和60年労働省(現厚生労働省)「労働基準研究会報告(労働基準法の「労働者」の判断基準について)」、平成23年厚生労働省「労使関係法研究会報告書(労働組合法上の労働者性の判断基準について)」に取りまとめられており、下図のとおりです。
| 労働基準法等 | 労働組合法 | |
| 判断基準 | 1・2を総合的に勘案することで、個別具体的に判断する。 1 使用従属性に関する判断基準 (1)指揮監督下の労働 ①仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無 ②業務遂行上の指揮監督の有無 ③拘束性の有無 ④代替性の有無 (2)報酬の労務対償性2 労働者性の判断を補強する要素 (1)事業者性の有無 ①機械、器具の負担関係 ②報酬の額 (2)専属性の程度 |
1をもとに、2と合わせて総合判断する。但し、3が認められる場合は、労働者性が否定され得る。
1 基本的判断要素 2 補充的判断要素 3 消極的判断要素 |
(2)労働基準法が適用されないための考慮要素ごとの対応策
各考慮要素の内容と労働基準法が適用されないための対応策は、一般的には、次のようになりますが、実際の裁判例をみると、業種ごとによって、注目すべき点が大きく異なる点に注意をすべきです業務委託により労働力を確保する際の労働基準法を中心とした注意点②。
① 業務依頼の諾否の自由
業務依頼の諾否の自由の有無は、最も重要な考慮要素の一つとされており、諾否の自由がある場合には、労働者性を否定し、諾否の自由がない場合には、労働者性を肯定する事情となります。
もっとも、包括的な仕事を依頼した際に、その中の一部の仕事について許諾の自由がないことは当然ですので、必ずしも労働者性を肯定する事情とはならないとされています。
対応策としては、包括的な仕事を依頼していない場合には、諾否の自由を与えることは当然です。
また、包括的な仕事を依頼している場合でも、諾否の自由を拒絶する場合には、契約類型や、契約の性質を慎重に検討する必要があります。
② 業務遂行上の指揮監督
業務遂行上の指揮監督の有無も、最も重要な考慮要素の一つとされており、指揮監督がない場合には、労働者性を否定し、指揮監督がある場合には、労働者性を肯定する事情となります。
もっとも、通常の業務委託においても少なからず注文者側からの指示はあるため、指揮監督の程度がその範疇にとどまる場合には、業務上の指揮監督とはいえないとされています。
対応策としては、まず、具体的な業務の遂行方法について指示をしないことがあげられます。
また、本来の業務の範囲外についての指示(ミーティングへの参加、服装の指定等)をしないことも重要です。
③ 拘束性
拘束性の有無も、重要な考慮要素の一つとされており、勤務場所や勤務時間の指定・管理がなされている場合には、労働者性を肯定し、そのような指定・管理がなされていない場合には、労働者性を否定する事情となります。
もっとも、業務の性質や安全管理等の事情から場所や時間が指定されることもあり、そのような場合には、労働者性を肯定する事情とはいえません。
勤務場所や勤務時間を指定する必要がある場合であっても、タイムカードなどによって従業員と同様に労働時間の管理まですることは避けるべきでしょう。
④ 代替性
業務委託先が再委託することや、補助者を使うことが許容されている場合には、労働者性を否定する事情に働きます。
この点は、業務委託契約を締結する際に、容易に対策が可能な点ですので、再委託を許容できる場合には再委託を許容し、再委託が許容できない場合でも、補助者について許容できる余地がないかを積極的に検討すべきです。
⑤ 報酬の労務対償性
時間報酬制や欠勤した場合に報酬の減額がある場合や、欠勤時に報酬の減額がある場合、いわゆる残業をした場合には通常の報酬とは別の手当が支給される場合には、報酬の性格が、使用者の指揮監督の下に一定時間労務を提供していることに対する対価と判断され、労働者性を肯定する事情として働きます。
対応策としては、報酬を歩合制とすることや、固定報酬とした場合でも欠勤控除や追加業務に対して、時間比例的に報酬の上乗せを行わないということがあげられます。
⑥ 機械、器具の負担関係
業務委託先が所有する機械、器具が高価な場合には、事業者としての性格が強く労働者性を弱める要素となります。
対応策としては、業務に必要な機械、器具を発注者側で用意、負担する度合いが強ければ強いほど業務委託先の事業者としての独立性が希薄になることから、これを避けるべきといえます。
やむを得ず発注者側で用意する場合には、費用を個別に計算し、報酬から天引きするなどの対処方法が考えられます。
⑦ 報酬の額
報酬の額が、正社員と比較して著しく高額である場合には、従業員に対する給与の支払いではなく、事業主に対する代金の支払いであると認められやすくなります。
もっとも、これは、単純に月の支払金額を比較するのではなく、業務委託先が負担する経費の額や、業務委託先の業務時間なども考慮されることになります。
対応策としては、根本的には、業務委託先との交渉を経た上で報酬を決定すべきといえます。
やむを得ず、発注者側で画一的に金額を決定する際は、想定される業務委託先が負担する経費の額と業務時間を考慮した上で業務委託先の時間給を算定し、その額が一般的な従業員の時間給を上回るような報酬を提示すべきでしょう。
⑧ 専属性
業務委託先が、契約上、あるいは、時間的余裕がなく事実上、他社からの業務を受注できていない場合は、経済的に特定の発注先に従属していると考えられ、労働者性を肯定する事情となります。
また、報酬に固定給がある又は事実上固定給となっており、その額が生計を維持しうる程度のものである場合には、報酬に生活保障的な要素が強く経済的に従属していると考えられ、労働者性を肯定する事情の一つとされています。
他方で、このような事情がないことをもって、労働者性を弱める事情とはならないとされています。
対応策としては、他社からの受注を禁止しないことや、勤務日や勤務時間にゆとりを持たせ、他社からの受注を可能にすること、可能な限り固定給制度を利用しないこと等があげられます。
⑨ その他の事情
採用時の選考過程が従業員採用の場合とほとんど同様であることや、報酬について、給与所得としての源泉徴収を行っていること、労働保険の適用対象としていること、服務規律を適用していること、退職金制度、福利厚生を適用していること等の、発注者が業務委託先を労働者と認識していると推認される点は労働者性を肯定する事情となります。
対応策としては、ハローワークなど雇用のため求人方法を用いず、求人を行う際には、業務委託であることを明確に示すこと、従業員用に使用している資料(給与明細、出勤簿、労働条件通知書等)を流用しないこと等があげられます。
3.労働基準法が適用されない場合
前記2.(2)の対応策を実施し、労働基準法が適用されない場合においても、何らの規制もないというわけではありません。
民法、商法のほか、労働組合法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)、下請代金支払等遅延防止法(下請法)、労働安全衛生法の一部(同法31条、31条の4等)、労災保険の特別加入制度(労働者災害補償保険法33条)などが適用されることがあります。
また、在宅しながら行うことができる業務を依頼する場合には、強制力はないものの「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン」に則った取引が望ましいです。
以下では、労働組合法、独占禁止法、下請法について、注意点を解説します。
(1)労働組合法上の注意点
前記2.(1)のとおり、労働組合法が適用される対象は、労働基準法と比べ広範ですので、労働組合を名乗る団体が成立している場合は当然として、業務委託先が団結する動きを見せた際にも注意が必要です。
発注者側から見れば、業務委託先が価格カルテル実施のための団体を結成しようとしていると見える場合であっても、労働組合法が適用されたときは、このことを理由に発起人である業務委託先との取引を打ち切る行為や、団体の結成を妨害する行為は、不当労働行為となってしまいます(労働組合法7条1号)。
不当労働行為とされた場合には、不当労働行為とされた法律行為は無効となるほか(最三小判昭43.4.9民集22巻4号845頁)、労働委員会による救済命令(労働組合法27条の12第1項)の対象となります。
救済命令に従わない場合には、50万円(金銭支払等の作為を命じる場合には、6日以上の遅滞で1日につき10万円を加算)以下の過料の制裁もあります(労働組合法32条後段)。
業務委託先が団結する動きを見せた場合や、労働組合を名乗る団体が団体交渉の申し入れをしてきた場合には、弁護士に相談の上、慎重な対応が必要です。
(2)独占禁止法上の注意点
公正取引委員会は、「個人としての働き方」の人材獲得分野における競争の確保のために、「人材と競争政策に関する検討会」を設置し、平成30年2月に検討会が報告書を発表しました。
同報告書では、発注者側の共同行為だけでなく、発注者単独の行為についても独占禁止法の適用を検討しており、労働基準法が適用されない分野を補完していることが注目されています。
同報告書によれば、優越的地位を濫用して不当に不利益を課す行為や事実と異なる優れた取引条件を提示することで、業務委託先を誤認させ、自らと取引をさせる行為等が、独占禁止法上の問題を生じさせるとされています。
ここでいう「優越的な地位」とは、業務委託先にとって発注者との取引の継続が困難になることが事業経営上大きな支障を来すため、発注者が業務委託先にとって著しく不利益な要請等を行っても、業務委託先がこれを受け入れざるを得ないような場合に認められます。
また、優越的地位を濫用して不当に不利益を課す行為の具体例として、以下のものが挙げられています。
- 機密保持義務、競業避止義務を課すこと
- 専属義務を課すこと
- 成果物の利用等を制限すること
(例)①成果物の出所表示の禁止②提供者による成果物の転用の禁止③発注者に業務委託先の肖像等の独占的利用権の付与④著作権の無償又は著しい低廉価格での譲渡要請
- 代金の支払い遅延、代金の減額要請及び成果物の受領拒否
- 著しく低い対価での取引要請
- 成果物に係る権利等について一方的に取り扱うこと
(例)①再利用時の対価を支払わない②業務委託先の肖像等を利用した際のロイヤリティについて、協議をせずに決定又は一切支払わないこと
- 発注者以外から業務委託先が得た収益の譲渡義務を課すこと
そして、不当に不利益を課しているかは、義務の内容や不利益の期間、代償措置の有無、業務委託先との協議状況、他の業務委託先の取引条件との差異などが考慮されるとされています。
業務委託先が労働者であるか判断が曖昧なケースでは、優越的な地位が認められるケースも少なくないでしょう。
そのため、上記に列挙した事項を実施する場合には、優越的な地位の有無や、不利益の程度、代償措置の有無などを検討し、十分な協議を経た上で、実施する必要があると言えるでしょう。
(3)下請法上の注意点
優越的地位が認められず、独占禁止法の適用がない場合であっても、資本金が一定規模の法人の親事業者(発注者)が、資本金が一定規模の下請事業者(業務委託先)に対して、一定の事項を委託する場合には、下請法が適用されます。
事業者の規模と、対象の委託内容は以下のとおりです(下請法2条7項、8項、下請法施行令1条)。
| 物品の製造・修理委託・ 情報成果物(プログラム)作成・ 役務(運送・物品の倉庫保管・情報処理)提供委託 |
その他の情報成果物作成・ その他の役務提供委託 |
||
| 親事業者 | 下請事業者 | 親事業者 | 下請事業者 |
| 3億円超 | 3億円以下 | 5千万円超 | 5千万円以下 |
| 1千万円超 3億円以下 |
1千万円以下 | 1千万円超 5千万円以下 |
1千万円以下 |
下請法の適用がある場合、親事業者は、下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払期日、支払方法等を記載した書面の交付義務があります(下請法3条1項)。
また、下請代金の支払期日は、給付の受領日から起算して、60日以内としなければなりません(下請法2条の2)。
その他、親事業者による受領拒否や代金の支払い遅延、代金の減額、返品、買いたたき、指定商品の強制購入、公益通報による不利益な取扱い、自己のために経済的利益を提供させること、給付内容の変更や、やり直しの要請が原則として禁止されています(下請法4条1項、2項)。
4.シェアリングエコノミー等における仲介事業の注意点
シェアリングエコノミー等における仲介事業者は、建前上は、注文者とワーカーとの間の業務委託を斡旋しているに過ぎません。
そのため、通常は、仲介事業者とワーカーとの間に雇用関係はおろか業務委託関係が生じることもなく、労働組合法や下請法等が適用されることもないでしょう。
しかし、シェアリングエコノミーにおいて、ワーカーに対する実質的な発注者は誰かという点については、必ずしも明確ではありません(平成30年3月雇用類似の働き方に関する検討会報告書)。
実態は仲介事業者とワーカーとの間の雇用や業務委託であるのに、各種法律の規制を潜脱する目的で斡旋という形式を取っていたとしても、法の適用を回避することはできないでしょう。
また、発注者が注文者であったとしても、万が一注文者とワーカーとの関係が雇用と認められてしまった場合には、職業安定法に違反して刑事罰が科されてしまうことに留意すべきです(職業安定法30条1項、64条1号)。
まとめ
以上に見てきたとおり、業務委託契約等によって事業のために不可欠な労働力を確保する場合には、労働基準法が適用されて不利益を被ることがないようにするために、業務依頼について諾否の自由を与える、業務遂行上の指揮監督を行わない、拘束をしない等を中心とした対策を講じることが不可欠です。
また、労働基準法が適用されない場合であっても、労働組合法、独占禁止法、下請法など、いくつかの法律が業務委託契約を規制することがあります。
このように、雇用によらずに、業務委託という形式で労働力を確保する際には、検討すべき事項が多数存在するため、労働分野に詳しい弁護士に相談することが望まれます。

※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
関連記事

パワーハラスメントの6類型とは?パワハラの実態と対処法も解説

スメルハラスメントで労災認定される?認定基準や注意点を解説

パワーハラスメント対策は義務!法改正の内容や対策方法を弁護士が解説






