企業法務のご相談も受付中。お気軽にお問合わせください。
改正民法について解説~意思能力・意思表示編~
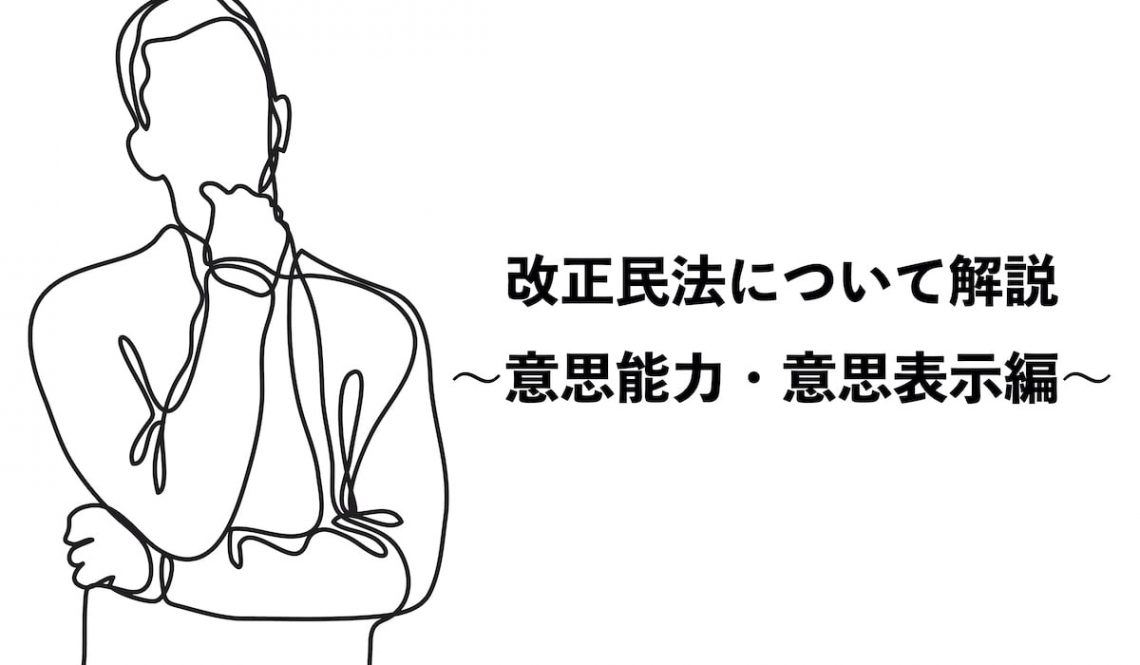
1.はじめに
令和2年4月1日、改正民法が施行されました。
本稿は、改正民法のうち、意思能力及び意思表示の部分について、主な改正のポイントと実務への影響について整理するものです。
2.意思能力及び意思表示とは
意思能力とは、行為の結果を判断するに足りるだけの能力をいいます。
また、意思表示とは、契約の申込みのように、一定の法律効果を欲する意思を表示する行為をいいます。
この意思能力の存否は、一定の年齢を超えれば認められるというように一律に決まるものではなく、個別具体的に判断されます。
ただし、一般的には、おおよそ7歳から10歳の知力とされています。
3.意思能力(改正民法3条の2)

(1)条文
| 【改正民法】
法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。 |
(2)改正のポイント
旧民法下では、明文規定はありませんでしたが、意思能力を欠く者の意思表示に基づく法律行為は、学説及び実務上無効であると解釈されており、判例も同様でした(大審院明治38年5月11日判決)。
しかし、判断能力の低下した高齢者をめぐるトラブルが増加しており、これに応える必要が生じていました。
そこで、改正民法3条の2が新設され、意思能力を欠く状態でなされた意思表示に基づく法律行為が無効であることが、明文化されました。
(3)実務への影響
実務上の解釈が明文化されたにとどまるため、改正による実務への影響は特にありません。
4.心裡留保(改正民法93条)

(1)条文
| 【旧民法】
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。 |
↓
| 【改正民法】
1 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。 2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 |
(2)改正のポイント
ア 心裡留保とは
心裡留保とは、意思表示を行う者(表意者)が、自己の真意と意思表示の内容が食い違っていることを知りながら意思表示を行うことをいいます。
例えば、冗談や励ましのつもりで、本当は10万円渡すつもりがないのに、「10万円あげるよ」と軽口をたたいたり、「10万円あげるから頑張れ」と言ったりした場合です。
イ 1項の改正
旧民法下では、心裡留保による意思表示は原則として有効であり、意思表示を受けた相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができた場合に、意思表示が無効となると定められていました。
この点、冗談とか単なる励ましであることが明らかである場合には話は別ですが、人の真意は分からないものです。
ですから、一度口にした内容を信頼した者を保護するべきですが、その内容が真意でないことを知っていたり、知ることができたりする場合にまで保護する必要はないと考えられます。
旧民法下で「真意を知り」と規定されていたことについて、相手方が表意者の真意の内容まで知る必要があるのか、真意の内容まで知らなくとも、真意と異なること自体を知り、又は知ることができたことで足りるのか、解釈が分かれていました。
改正民法では、相手方の真意の内容まで知らなくとも、相手方が真意と異なる意思表示をしていること自体を知り、又は知り得たことで足りるとされました。
ウ 2項の新設
旧民法下では、意思表示の無効を知らない第三者(善意の第三者)を保護する規定がありませんでした。
例えば、Aは土地の売買契約を締結するつもりがなく、BがAの真意を知っていたのにA→B→Cと土地が転売された場合、AB間では、Aが土地を売る気がないことをBは知っている以上、売買契約は無効となり、無効となったAB間の売買契約を前提にする以上、後に続くBC間の売買契約の効力も無効となりそうですが、この場合のCの保護について、旧民法下では解釈に委ねられていました。
この点について、判例(最高裁昭和44年11月14日判決)は、民法94条2項(虚偽表示による意思表示の無効は善意の第三者に対抗できないとの規定)を類推適用し、心裡留保による意思表示の無効は善意の第三者に対抗できないと解釈していました(なお、類推適用とは、直接定めた法律の規定がない場合に、最も類似した事項についての法律の規定を適用することをいいます。)。
即ち、上記例でいくと、CがAの真意を知らなければ、Cは土地の所有権を取得できるということです。
改正民法では、善意の第三者に意思表示の無効が対抗できないことが明文化されました。
(3)実務への影響
特に1項の改正により、相手方が真意と異なる意思表示をしていること自体を知り、又は知り得たことで法律行為は無効となるため、相手方の真意の内容まで立証しなくてもよいことが明確になりました。
5.錯誤(改正民法95条)

(1)条文
| 【旧民法】
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 |
↓
| 【改正民法】
1 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。 (1)意思表示に対応する意思を欠く錯誤 (2)表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤 2 前項第2号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。 3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取消しをすることができない。 (1)相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。 (2)相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。 4 第1項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。 |
(2)改正のポイント
ア 1項及び2項の改正
(ア)「要素」の意義
旧民法下では、法律行為の要素に錯誤があったときは、その法律行為は無効とされていました。
もっとも、「要素」の意味については、旧民法の条文上明らかではなく、判例(大審院大正7年10月3日判決、最高裁平成元年9月14日判決)は、意思表示の内容の主要な部分であり、この点について錯誤がなかったら表意者は意思表示をせず(因果性の要件)、かつ、意思表示をしないことが一般取引通念に照らして正当と認められること(重要性の要件)を指すと解釈していました。
改正民法では、「意思表示は、…錯誤に基づくものであって」(因果性の要件)、「その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき」(重要性の要件)を明文化し、「要素」の意義を明らかにしました。
(イ)無効から取り消しへの変更
改正民法では、法律行為の要素又は動機に錯誤があった場合に、その法律行為を無効とするのではなく、取り消すことができるものと変更されました。
(ウ)動機の錯誤
実務では、法律行為の「要素」、即ち法律行為の不可欠な要素をなす意思表示の重要な部分に錯誤がある場合よりも、意思表示をする動機に錯誤があった場合の法律行為の有効性が問題となる場合が多いです。
例えば、ある人が骨董屋に立ち寄ったところ、10万円で売られていた茶碗を見つけ、この茶碗は有名な陶芸家の作品であるからぜひ欲しいと思い、10万円で購入したが、実は無名な陶芸家の作品であったとします。
この場合、買主は、ある茶碗を10万円で購入する旨の意思表示をしたわけですが、当該茶碗の売買契約における重要な部分である「要素」(目的物が特定の茶碗であることとその茶碗が10万円の値段であること)には錯誤はなく、この茶碗を購入する動機に錯誤があるだけです。旧民法下では、この動機の錯誤についての取り扱いが不明確でした。
改正民法では、改正前の判例の流れに沿い、「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」(1項2号)、即ち動機の錯誤も法律行為の要素の錯誤の対象となるとともに、その動機が法律行為の基礎とされていることが表示されていたとき(2項)との要件の下に、動機の錯誤も取り消すことができることが明文化されました。
上記の例でいえば、買主が売主に対して有名な陶芸家の作品であるから購入するのだという動機が示されていた場合には売買契約を取り消せるということです。
これに対し、動機が表示されていなければ、売主は買主の動機を知りようがなく、このような場合にまで売買契約を取り消せるとすれば、売主に不測の不利益を与えることになるので取り消せません。
イ 3項の改正
旧民法下では、当事者双方が錯誤に陥っている場合(共通錯誤)について明文規定はありませんでした。
例えば、100万円の価値がある品物を、互いに10万円の価値しかないと誤解して売り買いした場合です。
改正民法では、共通錯誤があった場合には、相手方の信頼に配慮する必要はないため、その意思表示を取り消すことができると規定されました。
ウ 4項の新設
旧民法下では、第三者保護について明文規定を欠いていましたが、改正民法では、善意無過失の第三者が保護される旨明文化されました。
(3)実務への影響
錯誤があった場合、旧民法下では法律行為が「無効」となっていたものが、「取り消すことができる」に変更されたため、意思表示がなされたときから20年以内又は追認ができるときから5年以内に意思表示を取り消す旨の意思表示をしなければ、意思表示を取り消すことができなくなります(改正民法126条)。
このように、意思表示の有効性が取消しの期間制限にかかることには注意が必要です。
6.詐欺又は強迫(改正民法96条)

(1)条文
| 【旧民法】
1 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 第2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。 |
↓
| 【改正民法】
1 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 第2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。 |
(2)改正のポイント
ア 2項の改正
旧民法下では、例えば、A(第三者)がB(表意者)に詐欺を働いたために、BがC(相手方)と契約を行った場合には、Cが詐欺の事実を知っていたときに限り、Bの意思表示を取り消すことができるとされていました。
改正民法では、Cが詐欺の事実を知っていたときに限らず、知ることができたときにも、意思表示を取り消すことができるとされ、旧民法下に比べ、Bが厚く保護されることとなりました。
イ 3項の改正
旧民法下では、詐欺による意思表示を知らない第三者(善意の第三者)には、意思表示の取消しを主張できないとされていましたが、改正民法では、詐欺による意思表示を知らないことに加え、知らないことが過失に基づかないことも要求されることとなりました。
(3)実務への影響
民法の改正により、第三者が詐欺を働いた場合に、表意者は、相手方が詐欺の事実を知っていたか、知らなかったことに過失があることについての主張立証が必要となります。
また、表意者は、第三者の保護を否定するためには、その第三者が詐欺の事実を知っていたか、知らないことに過失があることについて主張立証が必要となります。
いずれの場合においても、改正民法では、過失の有無の争点が明文で加わったことになります。
7.意思表示の効力発生時期等(改正民法97条)

(1)条文
| 【旧民法】
1 隔地者間に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。 2 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 |
↓
| 【改正民法】
1 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。 2 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときは、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす。 3 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 |
(2)改正のポイント
ア 1項の改正
旧民法下では、隔地者(遠隔の地にある者)に対する意思表示について、相手方に到達したときに意思表示の効力が生じるとされていました。
改正民法では、隔地者間に限らず、対話者間でも、相手方に意思表示が到達したときに意思表示の効力が生じるとされました。
借家の借主が家賃を支払わなかった場合に、貸主が「滞納額全額を1週間以内に支払わなければ、契約を解除しよう」と考えた場合ですと、貸主が借主に面と向かって解除する旨を告げたり、電話で話したりする場合が対話者間の話であり、貸主が解除する旨の手紙を送ったり、電子メールで送信したりする場合が隔地者間の話になります。
改正民法では、両者において同じ取り扱いをすることが明文化されました。
もっとも、旧民法下において対話者間の意思表示の効力発生時期に明文の規定があったわけではなく、一般的に対話者間においても到達のときと考えられていたので、実質的な変更があったというわけではありません。
イ 2項の新設
改正民法では、意思表示の到達を相手方が正当な理由なく妨害したときは、意思表示の到達を擬制し、意思表示の効力が発生するとの規定が新設されました。
ウ 3項の改正
旧民法下では、意思表示の効力は、表意者が通知発送後に死亡し、又は行為能力を喪失しても維持されると規定されていましたが、改正民法では、民法3条の2の新設(意思能力を欠く者の法律行為の無効が明文化されたこと)を受け、表意者が意思能力を喪失した場合でも、意思表示の効力が維持されることが付け加えられました。
(3)実務への影響
特に、意思表示の到達を相手方が正当な理由なく妨害した場合の規定が新設されたことにより、相手方が意思表示の受領を拒絶した場合には、表意者は、相手方の妨害行為の存在と、その妨害行為が正当な理由に基づかないことについて、主張立証することが必要となります。
「正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げた」については、不在配達通知書により書留郵便の送付を知ったが受け取らなかったことのみで判断するのか、郵便の内容を十分に推知できたか否かの判断まで必要とするか、今後の解釈に委ねられています。
この点については、既に契約関係がある人からの郵便物なのか、全く面識のない人からの郵便物なのかといった、個別の事案に即して判断されることになるでしょう。
例えば、賃料を長期間滞納している借主が、貸主から送られてきた書留郵便の受け取りを拒否した場合には、正当な理由なく到達を妨げたといえる余地はあるように思われます。
8.意思表示の受領能力(改正民法98条の2)

(1)条文
| 【旧民法】
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。 |
↓
| 【改正民法】
意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に意思能力を有しなかったとき又は未成年者若しくは成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、次に掲げる者がその意思表示を知った後は、この限りでない。 (1)相手方の法定代理人 (2)意思能力を回復し、又は行為能力者となった相手方 |
(2)改正のポイント
旧民法下では、意思表示を理解する能力が不十分である未成年者及び成年被後見人が意思表示の相手方であった場合には、その意思表示を相手方に対抗できないとされていました。
改正民法では、民法3条の2の新設(意思能力を欠く者の法律行為の無効が明文化されたこと)を受け、相手方が意思能力を欠いていた場合にも、その意思表示を相手方に対抗できないことが付け加えられました。
また、改正民法では、未成年者が成年になったときや、成年被後見人が行為能力者となった場合には、意思表示を理解する能力は十分であると考えられることから、その意思表示を知った後は、意思表示を対抗できるとの規定を新設しました。
(3)実務への影響
改正による実務への影響は特にありませんが、旧民法下では解釈で補っていたことが多く、特に事後に意思能力を回復した場合については支配的な解釈が存在していなかったので、この点は明確になったといえます。
行為能力を有しない者に対して意思表示に基づく法律行為をする場合には後見人などの法定代理人の選任が必要となりますが、その申立は誰でもできるわけではありませんので、場合によっては訴訟提起をしたうえで特別代理人の選任を裁判所に求める必要があると思われます。
9.おわりに
本稿では、改正民法の意思能力及び意思表示の分野について、ポイントとなる点を整理しました。
改正民法が施行されたばかりである現在、改正民法の適用によって具体的事案がどのように解決されるかについては、今後の実務の積み重ねによって明確化する点も多々ございますので、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
関連記事

建築基準法改正(2019年施行)は生活やビジネスにどんな影響を及ぼすのか

賃貸借契約書の条項の意味は?弁護士が分かりやすく解説

会社法改正―【社外取締役活用等に向けた規律の見直し】






