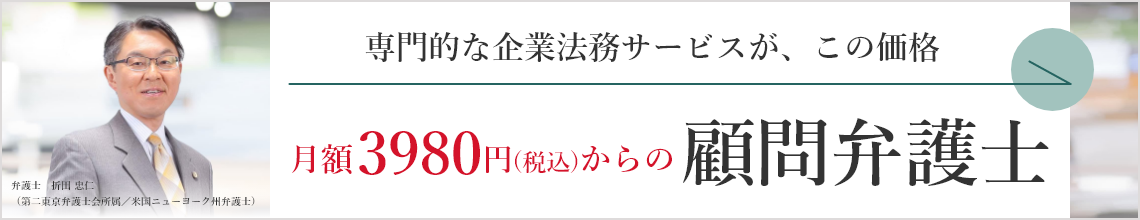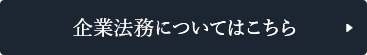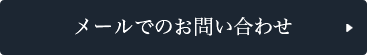企業法務のご相談も受付中。お気軽にお問合わせください。
特許権の侵害とは何か?侵害の判定方法と対抗措置についても解説
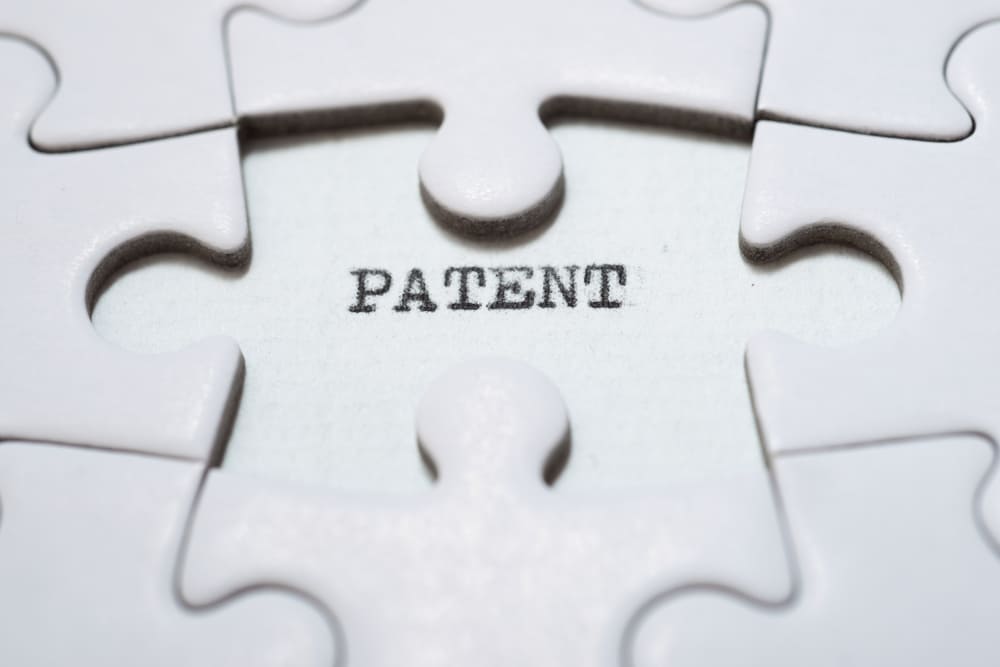
「特許権の侵害」は、よく耳にする言葉ですが、実際に侵害なのか否かは、慎重な判断を要します。
特許権を侵害されたと訴えても、単に類似しているだけでは該当しない可能性があるのです。
この記事では、特許権の侵害とは何かを明らかにするとともに、その判定方法と侵害された場合の対抗措置について解説します。
1.特許権の侵害とは
特許は、産業上利用することができる発明で、新規性と進歩性の2つの要件を満たすものをいいます(特許法29条)。
特許権者は、特許出願の日の翌日から原則として20年間、特許発明を独占的に実施できる権利があります(特許法68条)。
この場合の「実施」とは、次のような行為です。
- 物の発明にあっては、その物の生産、使用、譲渡等、輸出
- 方法の発明にあっては、その方法の使用
- 物を生産する方法の発明においては、その方法の使用
特許権者が独占的に実施できる「特許権」は、特許発明の技術的範囲に限ってその効力が及びます。
この、特許権の技術的範囲は、特許庁に提出した願書に添付した「特許請求の範囲」に基づいて決定されます(特許法70条1項)。
また文言の意義を解釈する際には、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮します(同条2項)。
第三者が、正当な権限なく、業として特許発明の技術的範囲に属する製品ないし方法について「実施」すれば、特許権の侵害となります。
特許権の侵害には、①文言侵害、②均等侵害、③間接侵害の3種類があります。
それぞれどのような侵害をいうのかみていきましょう。
(1)文言侵害
問題となる技術の内容が、特許発明の技術的範囲に属する場合、特許権の文言侵害となります。
そして、問題となる技術の内容が、特許発明の技術範囲に属する場合とは、「特許請求の範囲」として記載された内容の構成要件をすべて充足する場合をいいます。
つまり、その構成要件を一つでも満たしていなければ、文言侵害には該当しません。
(2)均等侵害
均等侵害は、「特許請求の範囲」として記載された内容と、問題となる技術の内容が一部異なっていても、同じ技術的範囲内にあり、実質的に同一であると判断される場合に成立します。
均等侵害が成立する基準は、最高裁の平成10年2月24日の判決において、次の5つが示されています。
- 技術と異なっている部分が、当該特許技術の本質部分でないこと
- 異なっている部分を置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の効果作用を奏するものであること
- 当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者であれば、容易に置き換えを思いつけたものであること
- 侵害が疑われる技術が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一ではなく、かつ当業者が容易に推考できないものであること
- 侵害が疑われている技術が、特許発明の特許出願手続きにおいて特許請求の範囲から意識的に除外されたものではないこと
(3)間接侵害
特許法101条では、特許発明の内容全体の実施に至らない場合でも、特許権侵害を誘発する可能性が高い態様の行為について、同条1号から6号までに列挙しています。
同条は、これらの行為を特許権侵害に該当すると定めています。
- 特許発明品の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等もしくは輸入または譲渡等の申出をする行為
- 特許発明品の生産に用いる物であって、その発明による課題の解決に不可欠なものについて、その生産、譲渡等もしくは輸入または譲渡等の申出をする行為
- 特許発明品を譲渡等または輸出のために所持する行為
- 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等もしくは輸入または譲渡等の申出をする行為
- 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物であってその発明による課題の解決に不可欠なものの生産、譲渡等もしくは輸入または譲渡等の申出をする行為
- 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を譲渡等または輸出のために所持する行為
2.特許権侵害を確認する手順
自社の開発製品が、特許権の侵害をしていないことについては、次のような流れで確認をしていきます。
(1)特許公報を入手する
特許権の侵害の有無は、特許公報の「特許請求の範囲」の記載内容に該当しているか否かで決まります。
そのため、特許侵害の可能性がある特許発明品の特許公報を入手することから始めます。
(2)「特許請求の範囲」を読み解く
記載内容への該当性は「特許請求の範囲」に記載された文言から判断されるため、ここに記載された技術要素をひとつひとつ分割して照合します。
分割した要素の中でひとつだけでも該当していない事項があれば、特許権の文言侵害はないと判断できます。
(3)均等侵害の可能性も検討
さらに検討を要するのが、均等侵害の有無です。
均等侵害は、特許請求の範囲として記載された内容と一部異なっていても、同じ技術的範囲内にあり、実質的に同一であると判断される場合に成立します。
そのため、過去の判例と照らし合わせて、均等侵害にも該当しないことを確認する必要があります。
3.特許権侵害に対抗するには
自社の特許権が侵害された場合、次のような対抗手段があります。
- 差止請求
- 損害賠償請求
- 刑事告訴
それぞれの進め方について解説していきましょう。
(1)差止請求
特許権者は、特許権を侵害する者に対し、その侵害の停止を請求することができます(特許法100条1項)。
これが差止請求です。
自社の被害を最小限に食い止めるには、迅速に差止請求を行う必要があります。
訴訟の結論を待ってからの差止請求は有効な効果が期待できないため、民事保全法に基づく仮処分を申し立てて、暫定的な差止めを求めます。
(2)損害賠償請求
故意または過失によって他人の権利を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負います(民法709条)。
特許権侵害によって売上への損害を被った場合、特許権者は侵害者に対して、損害賠償を請求できます。
特許権侵害の場合、損害額や過失の推定規定が設けられており、一般的な損害賠償請求よりも立証責任が緩和されています(特許法102条、103条)。
そのため、比較的容易に損害賠償請求をすることができます。
(3)刑事告訴
犯罪により害を被った者は、告訴をすることができます(刑事訴訟法230条)。
特許権侵害は犯罪に該当しますから、特許権者は、警察や検察に対して刑事告訴ができます。
特許権侵害についての罰則は、次のように定められています。
- 文言侵害・均等侵害(特許法196条)……→10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金または併科
- 間接侵害の法定刑(同法196条の2)……5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金または併科
法人の代表者・代理人・従業者などが、法人の業務に関して特許権侵害を犯した場合は、両罰規定として、法人にも3億円以下の罰金が科されます(同法201条1項1号)。
まとめ
特許権の侵害になるのは、次の要件に該当する場合です。
- 特許権が有効に存在している
- 実施が業として行われている
- 実施の内容が特許公報の「特許請求の範囲」の記載内容に該当している
- 実施をする正当な権限がない(特許権者からのライセンス許諾がない)
特許は、特許権が設定登録をされており、かつ出願した日の翌日から原則として20年以内であれば有効です。
特許権の侵害にあたるのは、実施を業として行った場合であり、個人の楽しみや家庭内で利用するために実施した場合は、特許権の侵害には該当しません。
特許権の侵害は、特許公報の「特許請求の範囲」に記載された文言から判断します。
ここに記載された技術要素の中で、ひとつだけでも該当していない事項があれば、特許権の文言侵害ではありません。
ただし、類似している場合は、均等侵害に該当しないかの検討が必要です。
均等侵害は、特許請求の範囲として記載された内容と一部異なっていても、同じ技術的範囲内にあり、実質的に同一であると判断される場合に成立します。最高裁の平成10年2月24日の判決などを参考にしてください。
自社の特許権が侵害された場合、➀差止請求、②損害賠償請求、③刑事告訴といった対抗措置があります。
これまで述べてきたように、特許権侵害か否かの判断は、専門技術的な判断を要します。
第三者に自分の発明が無断で使われているかもしれないと感じた方は、速やかに弁護士にご相談ください。
※この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
関連記事

特許の実施許諾契約とは?知的財産をビジネスに活用するポイント

二次的著作物を創作したら原著作者の権利はどこまで及ぶのか

商標権侵害とは?被害を受けたとき・権利を主張したいときの法的主張を解説